人生には避けて通れない事柄がいくつかあります。
その一つが「相続」です。
私たちは皆、いつか誰かから何かを相続するか、自分の財産を他人に相続させるかのどちらかを経験します。
そして、その相続の手続きは、しばしば複雑であり、感情的な困難を伴うことがあります。
また、相続と密接に関連しているのが「保険金」です。
生命保険金は、亡くなった方が生前に加入していた保険から支払われる金額で、これが相続財産の一部となることがあります。
しかし、保険金には特有の法律や規則があり、その取り扱いは一筋縄ではいきません。
本記事では、相続と保険金について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続とは
- 非課税枠のある生命保険金
- 生命保険金にかかる相続税の注意点
相続と保険金について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
- 1 相続とは何か?
- 2 相続税と生命保険
- 3 非課税枠のある生命保険金、ない生命保険金
- 4 生命保険金にかかる相続税の計算方法
- 5 生命保険金にかかる相続税の注意点
- 6 税理士に相談するメリット・デメリット
- 7 相続と保険金についてよくある質問
- 7.1 相続税の課税対象になる死亡保険金とは何ですか?
- 7.2 生命保険金は相続財産になりますか?
- 7.3 平等な相続を行うにはどうすればいいですか?
- 7.4 生命保険金を特別受益としたとき、遺留分はどのように計算するのですか?
- 7.5 相続人が死亡保険金を受け取ったときは、保険料を誰が払っていたのかを確認する必要がありますか?
- 7.6 相続税の課税対象になる死亡保険金の非課税限度額はどのように計算されますか?
- 7.7 相続税の課税対象になる死亡保険金の受取人は誰ですか?
- 7.8 死亡保険金を年金で受領する場合、どのように相続税が課税されますか?
- 7.9 相続人自身が保険料を負担していた場合、死亡保険金はどのように取り扱われますか?
- 7.10 受取人の利益が大きかった場合、他の相続人はどのように感じますか?
- 8 相続と保険金についてのまとめ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続とは何か?

相続とは、ある方が死亡したときにその方の財産や、すべての権利や義務を、特定の方が引き継ぐことを指します。
具体的には、
- 現金や預貯金
- 株式等の有価証券
- 車・貴金属等の動産
- 土地・建物等の不動産
- 借入金等の債務
- 賃借権・特許権・著作権等の権利
などが相続の対象となります。
相続には法定相続、遺言相続、分割協議相続の3つの方法があります。
- 法定相続:法定相続は、民法で規定された相続する権利を持つ方が相続します。
- 遺言相続:遺言相続では、遺言によって指定された相続方法が法定相続に優先します。
- 分割協議相続:分割協議相続では、相続人全員で協議して遺産の分割方法を決めます。
遺産分割協議は、具体的にどのように進めたらよいのか、その進め方や注意点などが重要です。
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須である点を押さえておきましょう。
遺産分割協議の成立には、必ず相続人全員の同意が必要です。
遺言書がある場合は遺言による相続となり、遺言書がない場合は法定相続となります。
また、全ての相続人が協議を行い、各々の状況に合わせて分配することも可能です。
相続の対象となる財産
相続の対象となる財産は、次のようなものがあります。
プラスの財産には、
- 現金や預貯金
- 株式等の有価証券
- 車・貴金属等の動産
- 土地・建物等の不動産
などが含まれます。
また、マイナスの財産には、
- 借入金等の債務
- 未払税金等
- 未払費用
などが含まれます。
しかし、身分に関連する権利や義務、または祭祀に関連する財産など、相続できない財産も存在します。
相続の対象とならない財産は次のようなものです。
- 一身専属的な権利義務(生活保護受給権、国家資格、親権、扶養義務など)
- 香典
- 弔慰金
- 葬儀費用
- 生命保険金(被相続人自身が保険金の受取人になっているものを除く)
などが該当します。
相続の手続き
相続の手続きは複雑であり、専門家への相談も検討することが推奨されています。
未成年者が相続人になる場合、未成年者には、代理人を立てる必要があります。
通常、代理人は親が務め、これを法定代理人といいます。
しかし、親と未成年の子供の両方が相続人であり、全ての相続人が遺産分割協議を行う場合など、親が未成年者の代理人として行動することができない状況も存在します。
このような場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続き書類の記入・捺印などを行うことになります。
相続の手続きについては、こちらの記事もお読みください。
相続について気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、相続について以下の点を中心にご紹介します! 相続の種類 相続に関係する税金とは 相続でよくあるトラブルとは 相続について理解するためにもご参考いた[…]
相続税と生命保険

生命保険は、私たちの生活を守る重要な道具の一つです。
しかし、その生命保険金が相続税の対象になることは、多くの方々が知らないかもしれません。
ここでは、相続税と生命保険の関係について詳しく説明します。
生命保険金とは
生命保険金は、保険契約者が亡くなった場合に支払われる金額のことを指します。
この生命保険金が相続税の対象になるかどうかは、保険契約の内容や受取人の状況によります。
相続税の非課税枠
生命保険金には、一定の条件を満たすと相続税の非課税枠が適用されます。
具体的には、保険契約者が死亡した時点で受取人が特定されている場合、その保険金は相続税の非課税枠の対象となります。
この非課税枠は、生命保険金の一部を相続税から免除するもので、一定の金額までの生命保険金は相続税の対象外となります。
この金額については、この記事で後述します。
基礎控除の適用
生命保険金が非課税枠を超えた場合でも、基礎控除が適用されることがあります。
基礎控除は、一定の金額までの相続財産を相続税から免除する制度です。
基礎控除額は、法定相続人の人数をもとに計算されます。
したがって、生命保険金が非課税枠を超えても、基礎控除の範囲内であれば相続税はかからないことになります。
しかし、基礎控除を超える部分については、相続税が課されます。
相続税の基礎控除額については、こちらの記事で解説していますので、あわせてお読みください。
相続税は、多くの方にとって複雑で気になる要素の一つではないでしょうか。 特に、「相続税はいくらからかかるのか」という疑問は、相続に直面した際に非常に重要です。 この記事では、相続税はいくらからかについて以下の点を中心にご紹介します![…]
生命保険金は遺産分割の対象にはならない
生命保険金は、一般的には遺産分割の対象にはなりません。
これは、生命保険金が保険契約者から直接受取人に支払われるためです。
したがって、生命保険金は遺産とは別のものとして扱われ、遺産分割の対象外となります。
しかし、これは一般的なルールであり、特定の状況下では異なる場合もあります。
例えば、保険契約者が受取人を指定していない場合や、受取人が死亡している場合などは、生命保険金が遺産として扱われる可能性があります。
このような場合、生命保険金は遺産分割の対象となり、相続人間で分割されることになります。
そのため、生命保険を選ぶ際や保険金を受け取る際には、遺産分割のルールを理解しておくことが重要です。
このように、生命保険金と相続税は密接に関連しており、適切な計画と理解が必要です。
生命保険は、相続税負担を軽減するための有効な手段となることがありますが、その利用方法や制度については専門家のアドバイスを求めることが重要です。
また、相続税制度は国や地域によって異なるため、具体的な対策は個々の状況に応じて検討する必要があります。
生命保険と相続税の関係について理解を深めることで、より安心した生活を送ることができるでしょう。
非課税枠のある生命保険金、ない生命保険金

生命保険金は、その受取人や保険料の負担者によって、相続税の課税対象となる場合とならない場合があります。
特に、非課税枠のある生命保険金と非課税枠のない生命保険金は、その計算方法や適用条件が異なります。
ここでは、これらの違いについて詳しく解説します。
それぞれの特性を理解することで、適切な保険選択や相続計画を立てることが可能となります。
非課税枠のある生命保険金
生命保険は、私たちの生活を守る重要なツールであり、その中でも非課税枠のある生命保険金は特に注目に値します。
非課税枠のある生命保険金とは、法定相続人が受け取る場合に限り、一定額まで非課税となる制度のことを指します。
具体的には、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。
この制度は、相続税の負担を軽減し、遺族の生活を支えるために設けられています。
しかし、この非課税枠を最大限に活用するためには、生命保険の受取人を適切に指定することが重要です。
なぜなら、非課税枠は受取人が法定相続人である場合にのみ適用されるからです。
また、配偶者は「配偶者の法定相続分または1億6000万円の高い方」まで相続税を非課税とすることが可能なため、配偶者を受取人に指定すると非課税枠を無駄にする可能性があります。
したがって、子供を受取人に指定することが、非課税枠を最も効果的に利用する方法と言えます。
非課税枠のない生命保険金
一方、非課税枠のない生命保険金について考えてみましょう。
非課税枠のない生命保険金とは、具体的には被保険者と保険料負担者が被相続人である生命保険金で、相続放棄をした相続人や、相続人でない方が受け取ったものに非課税枠は適用されません。
つまり、相続人でない孫や他の親族などを受取人とした生命保険は、それが非課税枠の範囲内であっても、非課税にならず、そのまま相続税がかかります。
このように、生命保険金の非課税枠は、相続税対策の一環として非常に有用ですが、その適用は受取人が法定相続人である場合に限られるため、生命保険の受取人を適切に指定することが重要です。
また、非課税枠のない生命保険金についても理解しておくことで、より適切な生命保険の選択と相続税対策が可能となります。
生命保険金にかかる相続税の計算方法

生命保険金は、その受取人や保険料の負担者によって、相続税の課税対象となる場合とならない場合があります。
特に、相続税の計算方法は、その適用条件や非課税枠の有無によって異なります。
ここでは、生命保険金にかかる相続税の計算方法について詳しく解説します。
個々の生命保険金にかかる相続税額
生命保険金にかかる相続税の計算は、一見複雑に見えるかもしれません。
しかし、その計算方法を理解すれば、生命保険金がどの程度の相続税負担につながるのかを把握することができます。
ただし、個々の生命保険金にかかる具体的な相続税額を計算することは難しいです。
なぜなら、相続税は全体の相続財産に対して計算され、その中で生命保険金が占める割合によって影響を受けるからです。
したがって、生命保険金一つ一つにかかる相続税の額を直接計算することはできません。
しかし、生命保険金が全体の相続財産の中でどの程度の割合を占めるか、そしてその生命保険金が相続税の対象となるかどうかを理解することで、生命保険金にかかる相続税の影響をある程度推測することが可能です。
生命保険金が相続税の対象になるかどうか
一方で、生命保険金が相続税の対象になるかどうかは明確に判断することができます。
具体的には、保険契約者と被保険者が同一で、保険金受取人が相続人である場合、その生命保険金は相続税の対象となります。
しかし、保険金受取人が相続人でない場合や、保険契約者と被保険者が異なる場合は、その生命保険金は相続税の対象外となる可能性があります。
このように、生命保険金が相続税の対象となるかどうかは、保険契約の内容や保険金受取人の状況によって決まります。
したがって、生命保険金に相続税がかかるかどうかを知るためには、自身の保険契約の内容を詳しく確認し、必要であれば専門家の意見を求めることが重要です。
課税される生命保険金の計算方法
生命保険金にかかる相続税の計算方法は、以下の手順で行われます。
まず、すべての相続人が受け取った保険金の合計額を計算します。
次に、その合計額から「500万円×法定相続人の数」を引きます。
この結果、その差額が正の場合、その部分が相続税の課税対象となります。
この計算方法により、生命保険金にかかる相続税の額を推定することができます。
しかし、この計算方法はあくまで一般的なものであり、具体的な計算は個々の状況や保険契約の内容によって異なるため、具体的な相続税の額を知るためには専門家の意見を求めることが最善です。
生命保険と相続税の関係は複雑であり、個々の状況により異なるため、具体的な対策を検討する際には専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
生命保険金にかかる相続税の注意点

生命保険金は、被相続人(亡くなった方)が被保険者となっている場合、その死亡後に相続人に支払われます。
この生命保険金には、相続税がかかるケースと、かからないケースがあります。
相続税がかかるケース
相続税がかかるのは、被相続人自身が保険料を負担し、その死亡をきっかけに保険金が支払われる場合です。
この場合、受け取られた保険金は、民法の観点からは相続財産とは認識されません。
しかし、相続税法では、「実質は相続で得た財産である」とみなされ、相続税の対象となります。
これを「みなし相続財産」といいます。
この時、非課税枠「500万円×法定相続人の数」を超える保険金が発生する場合、その保険金は相続税の対象です。
ただし、他のご遺産との状況や相続人の数によっては相続税がかからないことがあるので、ご自身の状況に応じて計算をする必要があります。
相続税がかからないケース
一方、生命保険金に相続税がかからないケースもあります。
具体的には、生命保険金の一定の金額が非課税となる枠が設けられています。
この非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」を上限としています。
注意点
生命保険金にかかる相続税には、いくつか注意点があります。
まず、相続放棄をした相続人が保険金受取人であった場合、非課税枠の適用そのものがなくなります。
また、孫が受け取った生命保険金は、相続税が2割加算されます。
「相続と生命保険の受取人」についての理解は、我々の生活における重要な側面です。 生命保険は、予期せぬ事態や将来の不確実性に備えるための重要なツールであり、その受取人の選択は、相続計画の一部として重要な役割を果たします。 本記事では、[…]
税理士に相談するメリット・デメリット
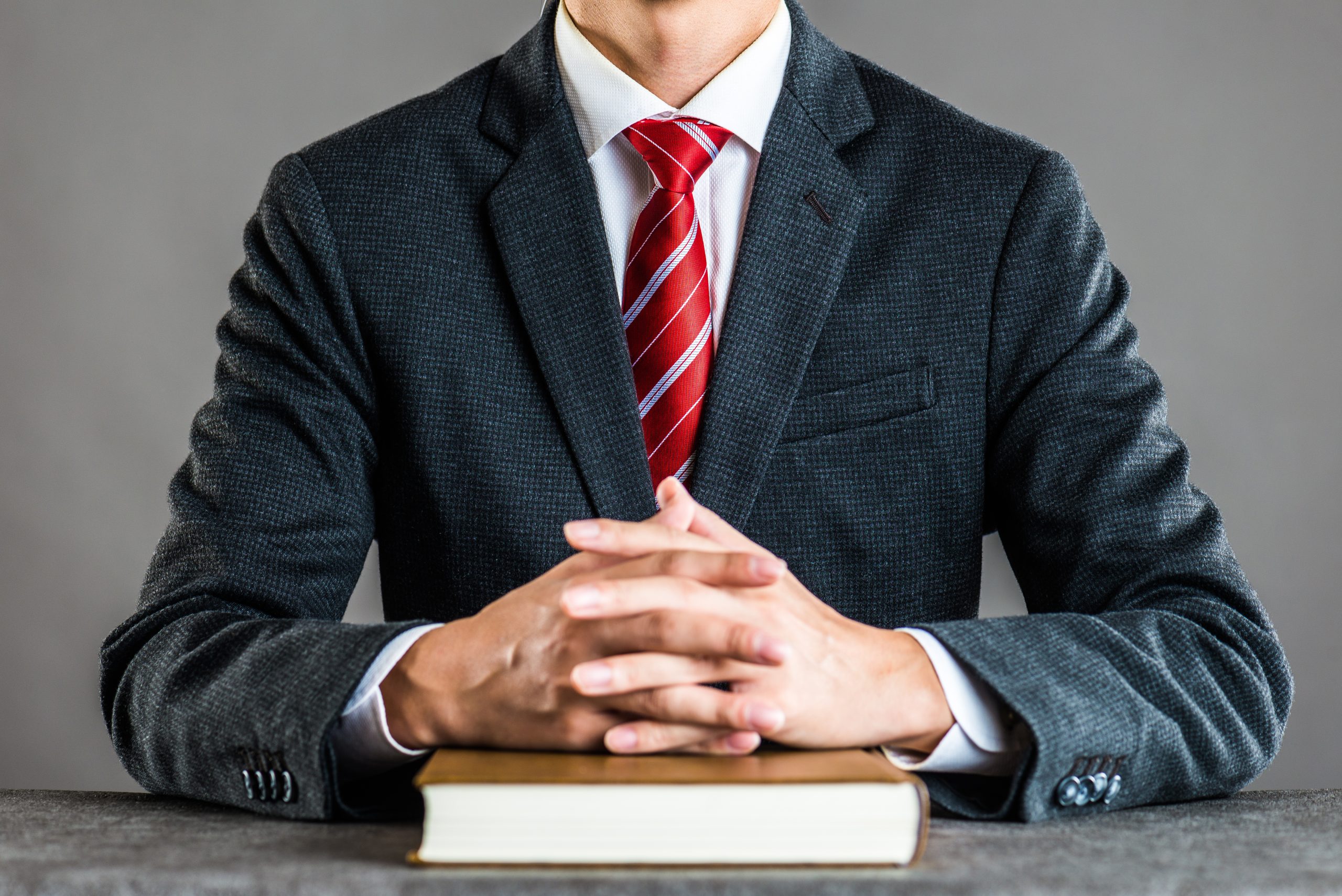
相続や保険金に関する問題は、専門的な知識を必要とする複雑なテーマです。
そのため、税理士に相談することで、適切なアドバイスや解決策を得ることができます。
しかし、税理士に相談することにはメリットだけでなく、デメリットも存在します。
ここでは、相続と保険金に関して税理士に相談するメリットとデメリットについて詳しく解説します。
メリット
税理士に相談するメリットはいくつか存在します。
以下で解説します。
専門的な知識
税理士は税法に関する専門的な知識を持っています。
相続税や保険金に関する複雑な問題を理解し、適切なアドバイスを提供することができます。
相続税や保険金に関する法律や規則が非常に複雑であり、一般的な人々が理解するのは困難であるため、非常に重要です。
節税対策
税理士は、相続税の節税対策を提案することができます。
これにより、相続税の負担を軽減することが可能です。
節税対策は、相続人が相続税を最小限に抑えるための戦略であり、適切な節税対策を立てることで、相続人は大きな経済的負担を避けることができます。
時間の節約
税理士に相談することで、自分で情報を調べたり、計算したりする時間を節約することができます。
これは、相続税や保険金に関する問題を解決するためには、多くの時間と労力が必要であるため、非常に有益です。
デメリット
税理士に相談する際、デメリットもいくつか存在します。
以下で解説します。
費用
税理士に相談するためには、相談料が必要です。
この費用は、相続財産の価値や相談内容によります。
しかし、この費用は、相続税の節税対策を立てることで得られる経済的な利益と比較すると、通常は小さいものです。
信頼性
税理士によっては、自分の利益を優先する可能性があります。
そのため、信頼できる税理士を見つけることが重要です。
信頼できる税理士を見つけるためには、口コミや評判、専門的な資格や経験などを確認することが有効です。
相続と保険金についてよくある質問

相続と保険金に関する疑問は多岐にわたり、適切な情報を得ることが重要です。
以下は、相続と保険金についてよくある質問とその回答をまとめたものです。
相続税の課税対象になる死亡保険金とは何ですか?
死亡保険金は、被相続人の死亡によって取得した損害保険金や生命保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られる)で、保険料の全部、または一部を被相続人が負担していたものは相続等により取得したとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、非課税枠が設けられているため、条件に当てはまる場合は相続税の対象となりません。
生命保険金は相続財産になりますか?
生命保険金は、原則として相続財産にはなりません。
しかし、生命保険金の受取人が被保険者本人である場合には相続財産となります。
平等な相続を行うにはどうすればいいですか?
生命保険金を一部の相続人しか受け取れない場合、他の相続人にとっては、公平でないと感じられる可能性があります。
この状況で相続人間の公平性を保つために、「特別受益」「寄与分」「遺留分」が用いられます。
生命保険金を特別受益としたとき、遺留分はどのように計算するのですか?
生命保険金が特別受益とみなされる場合、その金額は原則として他の相続財産と合計して遺留分を計算します。
具体的には、遺留分を算定するための遺産の価額に生命保険金を加えることを意味します。
これにより、遺留分権利者が取得する遺留分が増えることになります。
また、遺留分を算定するための計算方法は、「被相続人(亡くなった方)の亡くなった時点で有している財産額」に「相続開始前1年間にした贈与の額」及び「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の債務の額」を控除した額を出します。
相続人が死亡保険金を受け取ったときは、保険料を誰が払っていたのかを確認する必要がありますか?
保険料を誰が払っていたのかを確認することは重要です。
これは、保険料を負担していた方によって、かかる税金の種類が異なるためです。
相続税の課税対象になる死亡保険金の非課税限度額はどのように計算されますか?
相続人が死亡保険金の受取人である場合、全ての相続人が受け取る保険金の総額が計算式により算出された非課税限度額を超えた場合、その超過分は相続税の対象となります。
非課税限度額の計算式は「500万円 × 法定相続人の数」です。
相続税の課税対象になる死亡保険金の受取人は誰ですか?
受取人が被保険者の相続人であるときは相続により取得したものとみなされ、相続人以外の方が受取人であるときは、遺贈により取得したものとみなされます。
死亡保険金を年金で受領する場合、どのように相続税が課税されますか?
年金方式で死亡保険金を受け取る際は、その年金受給権に相続税がかかります。
例えば、収入保障保険からの年金受給権の価値が相続税の対象になります。
さらに、公的年金以外の年金を毎年受け取る場合、その年金の所得に対する所得税は、年金の収入を課税対象部分(年金受給権に該当する部分とその他の部分)と非課税部分に分けて計算されます。
相続人自身が保険料を負担していた場合、死亡保険金はどのように取り扱われますか?
相続人自身が保険料を負担していた場合、死亡保険金は一時所得として取り扱われます。
この場合、受け取った保険金やそれまでに負担した保険料などに基づき、一時所得を計算します。
受取人の利益が大きかった場合、他の相続人はどのように感じますか?
生命保険金の受取人が、生命保険の金額が大きい場合や、他にも多額の利益を被相続人から受け取っていたりする場合には、他の相続人としては不公平を感じてしまうという方も多いとされています。
相続と保険金についてのまとめ

ここまで、相続と保険金についてお伝えしてきました。
相続と保険金についての要点をまとめると以下の通りです。
- 相続とは、ある方が死亡したときにその方の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐこと
- 非課税枠のある生命保険金は、具体的には「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となる
- 生命保険金にかかる相続税の注意点は、「相続放棄をした相続人が保険金受取人であった場合、非課税枠の適用そのものがなくなる」「孫が受け取った生命保険金は、相続税が2割加算される」
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




