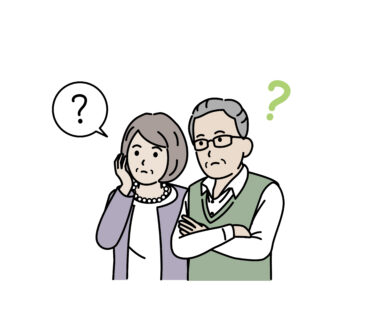戸籍謄本は本籍地での取得が一般的ですが、現住所や遠方からでも手に入れる方法があります。近年では郵送やオンライン申請、さらには全国の役所窓口での交付が可能となり、手続きの利便性が向上しています。
戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法について以下の点を中心にご紹介します!
- 戸籍謄本の取得方法
- 本籍地以外で取得する方法
- 代理人が取得する場合
戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、戸籍の内容を全て記載した公的な証明書です。戸籍には、日本国民の 出生、婚姻、離婚、死亡、親子関係 など、個人の身分事項が記録されています。これにより、 家族構成や本籍地、氏名の変更履歴 などが把握でき、 法的な身分関係を証明する重要な書類 となります。
相続手続きや婚姻届、各種法的な申請の場面で戸籍謄本は必要になることが多く、特に 相続手続き では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの 連続した戸籍謄本 の提出が必要です。これにより、相続人の特定や 法定相続分 の確認が行われます。
戸籍謄本は、 本籍地の市区町村役場 にて取得できます。また、戸籍に記録された一部の情報を証明する 戸籍抄本 という形式もありますが、戸籍謄本は 戸籍内の全員の情報 を記載したものとなります。
戸籍謄本がどんなものなのか皆さんご存じですか? なかなか使う機会がないのでなんとなくしか知らないという方が多いのではないでしょうか。 戸籍謄本とは、という基本的なことから戸籍謄本が必要な時はいつなのか、取得方法などについて詳しく解説[…]
戸籍謄本と戸籍抄本の違い

戸籍謄本と戸籍抄本は、いずれも戸籍に記載された情報を証明する公的書類ですが、記載内容と用途に違いがあります。
戸籍謄本(全部事項証明書)
戸籍に記載されている 全員の情報 がすべて記載された書類です。本籍地、世帯主、家族構成、出生、婚姻、離婚、養子縁組などの情報が含まれます。
相続手続き、結婚手続き、パスポートの申請 など、幅広い場面で使用されます。
戸籍抄本(個人事項証明書)
戸籍に記載されているうち、 特定の個人の情報のみ を抜粋した書類です。抄本は、個人に関する特定の情報を証明する場合に使用されることが多いですが、 相続手続き では原則として 戸籍謄本 の提出が必要です。
主な違いまとめ
| 項目 | 戸籍謄本 | 戸籍抄本 |
| 記載内容 | 戸籍に記載された全員の情報 | 戸籍に記載された個人の情報 |
| 用途 | 相続手続き、結婚手続きなど | 個人の身分関係証明 |
| 必要書類 | 相続手続きで必要 | 必要な場面は限定的 |
相続手続きで必要な戸籍謄本の種類
相続手続きを進める際には、被相続人(亡くなった方)と相続人の 戸籍謄本 を揃える必要があります。特に、被相続人の 出生から死亡までの連続した戸籍謄本 を取得することが重要です。これにより、相続人を特定し、 法定相続分 の確認が行われます。
被相続人の戸籍謄本
- 出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人が 生まれたときの戸籍 から 死亡時の戸籍 までのすべての戸籍謄本を収集します。 - 除籍謄本(被相続人が除籍された際に作成される)
- 改製原戸籍(戸籍の改製により変更された場合)
相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人の 最新の戸籍謄本 を取得し、身分関係を証明します。
取得すべき戸籍謄本の種類まとめ
| 書類名 | 説明 | 取得理由 |
| 出生時の戸籍謄本 | 被相続人の出生を証明 | 相続人を確定するため |
| 婚姻時の戸籍謄本 | 結婚や離婚の有無を証明 | 配偶者の相続権を確認するため |
| 除籍謄本 | 被相続人が死亡したことを証明 | 相続手続きを進めるため |
| 相続人の戸籍謄本 | 各相続人の身分関係を証明 | 相続人の権利を確定するため |
戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本は、相続手続きや各種公的手続きにおいて必要になる重要な書類です。取得方法にはいくつかの手段があり、状況に応じて適切な方法を選ぶことができます。以下では、具体的な取得方法を詳しく解説します。
役所の窓口で請求する
本籍地の市区町村役場の窓口で、戸籍謄本を直接請求する方法です。役所の営業時間内であればその場で取得できます。
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 手数料(自治体によりますが、一般的に450円程度)
- 印鑑(自治体によっては不要な場合もあります)
手続きの流れ
- 本籍地の役所の窓口に行く
- 申請書に必要事項を記入し、窓口に提出
- 本人確認書類を提示し、手数料を支払う
- その場で戸籍謄本を受け取る
郵送で請求する
本籍地が遠方にある場合は、郵送で戸籍謄本を請求することも可能です。時間はかかりますが、窓口に行けない場合に便利です。
必要なもの
- 申請書(各自治体の公式サイトからダウンロード可能)
- 本人確認書類のコピー
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
- 返信用封筒(切手を貼付し、返送先住所を記入)
手続きの流れ
- 必要書類を用意し、本籍地の市区町村役場に郵送
- 役所で手続きを行い、郵送で戸籍謄本を返送してもらう
- 数日から1週間程度で届く
コンビニで請求する
一部の自治体では、マイナンバーカードを利用して、コンビニ交付サービスで戸籍謄本を取得できます。
利用可能なコンビニ
- セブンイレブン
- ファミリーマート
- ローソンなど
必要なもの
- マイナンバーカード
- 4桁の暗証番号
手続きの流れ:
- コンビニのマルチコピー機で「行政サービス」を選択
- マイナンバーカードを読み取り、暗証番号を入力
- 必要な書類を選び、手数料を支払って印刷
※対応している自治体のみ利用可能です。事前に自治体の公式サイトで確認してください。
代理人が請求する
代理人による戸籍謄本の請求も可能ですが、委任状が必要です。
必要なもの
- 委任状(請求者が作成)
- 代理人の本人確認書類
- 手数料
手続きの流れ:
- 代理人が必要書類を持参して、役所の窓口で請求
- 役所で書類を確認後、戸籍謄本を発行
※代理人による請求では、委任状の不備がないように注意してください。
戸籍謄本はどこで取得できるのかについて気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、戸籍謄本について以下の点を中心にご紹介します! 戸籍謄本が取れる場所 相続手続きで戸籍謄本が必要になる時 […]
戸籍謄本を取得するのにかかる費用

戸籍謄本を取得する際には、手数料が発生します。手数料は、戸籍謄本の発行を依頼する方法や自治体によって異なりますが、一般的な費用の目安は以下の通りです。
1. 役所の窓口で取得する場合
手数料:450円~750円程度(1通)
戸籍謄本の取得にかかる費用は、通常450円前後ですが、自治体によっては異なる場合があります。
- 東京都:450円
- 大阪府:450円
- 北海道:500円~600円
役所の窓口で取得する場合は、申請時に現金で支払います。
2. 郵送で取得する場合
手数料:450円程度 + 郵送費用
郵送での取得では、手数料のほかに郵便料金と定額小為替の購入費用がかかります。
- 定額小為替の発行手数料:1枚につき 200円(郵便局で購入)
- 返信用封筒の切手代:84円~140円程度(封筒のサイズや重さによる)
例:450円(手数料) + 200円(定額小為替手数料) + 84円(切手代) = 734円程度
3. コンビニで取得する場合
手数料:450円~500円(1通)
コンビニで取得する場合は、自治体によって手数料が異なる場合があります。マイナンバーカードが必要で、マルチコピー機で申請・支払いを行います。
- セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどで取得可能。
- コンビニ交付サービスを利用している自治体に限ります。
4. 代理人が取得する場合
手数料:450円~750円程度(1通)
代理人による取得でも、基本的な手数料は窓口申請と同じです。
ただし、委任状の作成が必要であり、代理人が役所まで行くための交通費が別途かかることがあります。
費用のまとめ表
| 取得方法 | 手数料(1通) | その他の費用 | 合計費用の目安 |
| 役所の窓口 | 450円~750円 | なし | 450~750円 |
| 郵送 | 450円 | 定額小為替手数料、切手代 | 700円~900円程度 |
| コンビニ | 450円~500円 | マイナンバーカードが必要 | 450円~500円 |
| 代理人による取得 | 450円~750円 | 交通費、委任状作成費用など | 500~1,000円程度 |
注意点
- 自治体によって手数料が異なるため、事前に確認することが重要です。
- 郵送請求の場合、返信用封筒には切手を貼り、正確な住所を記載してください。
- コンビニ交付サービスは、利用可能な自治体のみで対応しているため、自治体の公式サイトで確認してください。
取得費用は請求方法によって異なるため、自分に合った方法を選び、必要な費用を事前に把握しておくことが大切です。
戸籍謄本を取得する際には、証明書交付手数料がかかります。自治体によって手数料の金額や手続き方法が異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。 本記事では戸籍謄本の証明書交付手数料はいくらかについて以下の[…]
戸籍謄本を本籍地以外でとる方法

戸籍謄本は、通常は本籍地のある市区町村役場で取得しますが、本籍地が遠方の場合には、本籍地以外の役所やコンビニで取得することが可能です。これは、広域交付制度やコンビニ交付サービスを利用することで実現します。
以下では、戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法について詳しく解説します。
戸籍謄本を本籍地以外で取得する流れ
戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法には、主に以下の手順があります。
1. 広域交付制度を利用する
広域交付制度を利用することで、本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取得できます。この制度を利用するには、マイナンバーカードが必要です。
手続きの流れ
- 最寄りの役所に行く
- マイナンバーカードを提示して、戸籍謄本の交付申請を行う
- 本籍地の役所に照会が行われ、照会が完了すると戸籍謄本が発行される
2. コンビニ交付サービスを利用する
コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードを利用して、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどのコンビニで戸籍謄本を取得できるサービスです。
手続きの流れ
- コンビニのマルチコピー機で「行政サービス」を選択
- マイナンバーカードを読み取り、暗証番号を入力する
- 必要な書類を選択し、手数料を支払ってその場で印刷
戸籍謄本を本籍地以外で取得するのにかかる費用
本籍地以外で戸籍謄本を取得する場合、手数料は通常の取得方法と同じです。ただし、利用する方法によって若干の違いがあります。
| 取得方法 | 手数料(1通) | その他の費用 |
| 広域交付制度 | 450円~750円 | マイナンバーカードが必要 |
| コンビニ交付サービス | 450円~500円 | マイナンバーカードが必要 |
※手数料は自治体ごとに異なる場合があります。
戸籍謄本を本籍地以外で取得する手続きに必要なもの
戸籍謄本を本籍地以外で取得するためには、いくつかの必要書類があります。利用する方法によって異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。
1. 広域交付制度を利用する場合
- マイナンバーカード(必須)
- 暗証番号(マイナンバーカード作成時に設定したもの)
- 手数料(450円~750円)
2. コンビニ交付サービスを利用する場合
- マイナンバーカード(ICチップが搭載されているもの)
- 暗証番号(4桁の数字)
- コンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機
※代理人による請求は、広域交付制度では利用できません。
戸籍謄本を本籍地以外で取得する場合は、事前に利用する役所やコンビニでの対応状況を確認し、必要な書類を忘れずに持参することが大切です。マイナンバーカードを活用することで、より簡単に戸籍謄本を取得できるので、手続きが煩雑になるのを防ぐことができます。
戸籍謄本代理人が取得する場合

戸籍謄本は、原則として本人または法定代理人が取得できますが、代理人が取得することも可能です。その際には、委任状の提出が必要になります。代理人が取得するケースでは、正しい手続きと必要書類を準備することが重要です。
戸籍謄本を請求できる人
戸籍謄本は、以下の人が取得できます。
1. 本人
戸籍の記載内容に関する権利を有する本人は、自分の戸籍謄本を請求することができます。
2. 配偶者や直系の親族
配偶者、親、子などの直系親族も、本人に代わって戸籍謄本を取得できます。
3. 法定代理人
未成年者や成年被後見人など、法定代理人として権限を有する人が取得できます。
4. 委任を受けた代理人
委任状を用意すれば、第三者が代理人として戸籍謄本を請求できます。
例えば、相続手続きを進めるために、司法書士や行政書士が代理で請求するケースがあります。
委任状について
委任状とは、本人が代理人に対して戸籍謄本の取得を委任することを証明する書類です。代理人による請求には、委任状の提出が必須です。
委任状の記載内容
委任状には、以下の内容を必ず記載します。
- 委任者の情報(氏名、住所、生年月日)
- 代理人の情報(氏名、住所、生年月日)
- 委任する内容
- 例:「○○市役所において、○○の戸籍謄本を取得することを委任します」
- 委任者の署名・押印
- 委任者本人が直筆で署名し、実印または認印を押します。
委任状の注意点
- 委任状には、必ず委任者の署名が必要です。
- 代理人が複数の戸籍を請求する場合は、戸籍ごとに具体的に記載する必要があります。
- 委任状の形式は特に決まっていませんが、必要事項が漏れないように注意しましょう。
委任状の提出方法
- 代理人は、委任状と本人確認書類を持参し、本籍地の役所に提出します。
代理人の本人確認書類
代理人が窓口で提出する際には、以下の本人確認書類が必要です。
| 書類の種類 | 例 |
| 1点で認められる書類 | 運転免許証、マイナンバーカード |
| 2点必要な書類 | 健康保険証、年金手帳など |
戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法に関するよくある質問

本籍地以外で戸籍謄本を取得することは可能?
本籍地以外でも戸籍謄本を取得することは可能です。通常、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場でしか取得できませんが、近年の法改正により、広域交付制度の導入やコンビニ交付サービスの利用が進み、本籍地以外の役所やコンビニでも取得できるケースが増えています。
以下では、具体的な方法について解説します。
1. 広域交付制度を利用して取得する
2024年の戸籍法改正により、広域交付制度が導入され、本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。この制度により、遠方にある本籍地に行かなくても最寄りの役所で戸籍謄本を請求できます。
【広域交付制度の利用条件】
- 対象者:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)
- 必要書類:マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き本人確認書類
- 手数料:1通あたり450円~750円(自治体によって異なる)
【利用方法】
- 最寄りの市区町村役場の窓口に行く
- 本人確認書類を提示し、戸籍謄本の交付を申請する
- 本籍地の役所に照会が行われ、確認が取れ次第、戸籍謄本が発行される
※代理人による申請や郵送請求は、この制度では利用できません。
2. コンビニ交付サービスを利用する
本籍地以外で戸籍謄本を取得するもう一つの方法は、コンビニ交付サービスを利用することです。
対応している自治体であれば、全国の主要なコンビニで戸籍謄本を取得することができます。
【必要なもの】
- マイナンバーカード
- 暗証番号
【手続きの流れ】
- セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどのマルチコピー機を利用
- 「行政サービス」から戸籍証明書の交付を選択
- マイナンバーカードを読み取り、暗証番号を入力
- 必要な戸籍謄本を選び、手数料を支払ってその場で印刷
【注意点】
- 利用できる自治体は限られています。
- 本籍地がある自治体がコンビニ交付サービスに対応しているか事前に確認しましょう。
3. 郵送で請求する場合は本籍地のみ
本籍地以外から郵送で戸籍謄本を請求することはできません。
郵送請求をする場合は、本籍地の市区町村役場に直接送付する必要があります。
まとめ
| 方法 | 取得可能な場所 | 必要な書類 | 手数料 |
| 広域交付制度 | 最寄りの役所 | 本人確認書類 | 450円~750円 |
| コンビニ交付サービス | 全国の主要コンビニ | マイナンバーカード | 450円~500円 |
| 郵送請求 | 本籍地の役所のみ | 申請書、手数料 | 450円~750円+郵送費 |
本籍地以外で戸籍謄本を取得する方法は複数ありますが、広域交付制度やコンビニ交付サービスを活用することで、より簡単に取得することができます。自分に合った方法を選び、必要な手続きをスムーズに行いましょう。
戸籍謄本が取得できるコンビニは?
戸籍謄本は、マイナンバーカードを利用することで、全国の主要なコンビニエンスストアで取得することができます。このサービスを提供しているコンビニには、マルチコピー機が設置されており、手軽に必要な書類を印刷することが可能です。
以下は、戸籍謄本を取得できる主なコンビニの一覧です。
戸籍謄本が取得できる主なコンビニ
セブンイレブン
全国各地に店舗があり、マルチコピー機を設置している店舗で利用可能です。
ファミリーマート
マルチコピー機を利用して、戸籍謄本を取得できます。一部店舗では設置がない場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。
ローソン
全国のローソン店舗でも、マルチコピー機を利用して戸籍謄本の取得が可能です。
ミニストップ
ミニストップでも、同様にマルチコピー機から戸籍謄本を取得できます。
コンビニで戸籍謄本を取得する流れは?
コンビニ交付サービスを利用すれば、全国の主要なコンビニエンスストアで、マルチコピー機を使って戸籍謄本を簡単に取得することができます。利用にはマイナンバーカードが必要で、利用時間も長いため、役所に行く時間がない人にとって便利なサービスです。
以下では、コンビニで戸籍謄本を取得する具体的な流れを詳しく解説します。
相続手続きにおいて、戸籍謄本は相続関係を証明するために必要不可欠な書類です。戸籍謄本には、出生、結婚、死亡などの親族的な身分関係や本籍地が記載されています。相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。
戸籍謄本の取得方法
- 役所の窓口で請求: 本籍地のある役所の窓口で申請します。申請時には、手数料、印鑑、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)が必要です。
- 郵送で請求: 本籍地が遠方の場合、郵送での請求が可能です。請求書、本人確認書類
2. 配偶者や直系の親族
配偶者、親、子などの直系親族も、本人に代わって戸籍謄本を取得できます。
3. 法定代理人
未成年者や成年被後見人など、法定代理人として権限を有する人が取得できます。
4. 委任を受けた代理人
委任状を用意すれば、第三者が代理人として戸籍謄本を請求できます。
例えば、相続手続きを進めるために、司法書士や行政書士が代理で請求するケースがあります。
戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法のまとめ

ここまで戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法についてお伝えしてきました。
戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法の要点をまとめると以下の通りです。
- 役所での請求や郵送で請求するなど
- 本籍地が遠方の場合には、本籍地以外の役所やコンビニで取得することが可能
- 代理人による請求には、委任状の提出が必須
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。