2024年4月1日から施行される相続登記の義務化は、日本の相続制度において大きな変革をもたらします。
従来の制度では任意であった相続登記が、今後は義務化されることで、相続人は相続発生後一定期間内に登記手続きを行わなければならなくなります。
この新制度の背景には、所有者不明土地の増加や、不動産取引の透明性向上の必要性があり、多くの人々にとって重要な影響を及ぼすことが予想されます。
本記事では、相続登記義務化について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続登記とは
- 相続登記義務化
- 相続登記義務違反
相続登記義務化の手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続登記とは

相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことを指します。
日本における不動産の所有権は、法務局が管理する登記簿(登記記録)に記載されているため、相続が発生した際にはこの記録を更新する必要があります。
- 不動産の名義変更: 相続によって不動産を受け継いだ場合、その所有者を法的に明確にするために登記が必要です。
- 法的手続きの重要性: 登記簿の記録は、不動産の売買や担保設定、利用において非常に重要であり、正確な名義人が記録されていないと不動産取引が困難になります。
- 相続人の義務: 相続人は、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請しなければなりません。
これにより、被相続人から自分の名義に変更することができます。
相続登記の必要性とリスク
相続登記を適切に行わないと、相続人にさまざまなリスクが生じます。
- 権利関係の複雑化: 長期間登記をしない場合、次世代の相続が重なり、相続人が増えることで権利関係が非常に複雑になります。
これにより、相続登記自体が難しくなる可能性があります。 - 不動産の売却や担保設定の困難: 登記簿上の所有者が被相続人のままでは、不動産を売却したり担保として提供したりすることができません。
- 差し押さえのリスク: 相続人の中に借金を抱えている人がいる場合、その持分が差し押さえられるリスクがあります。
債権者は代位登記を利用して相続登記を行い、持分を差し押さえることができます。
相続登記は、不動産の権利を法的に保護するために欠かせない手続きです。
2024年4月1日から義務化されることにより、所有者不明土地問題の解消が期待されます。
相続人は早めに手続きを行い、リスクを回避することが重要です。
疑問や不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
相続登記義務化について
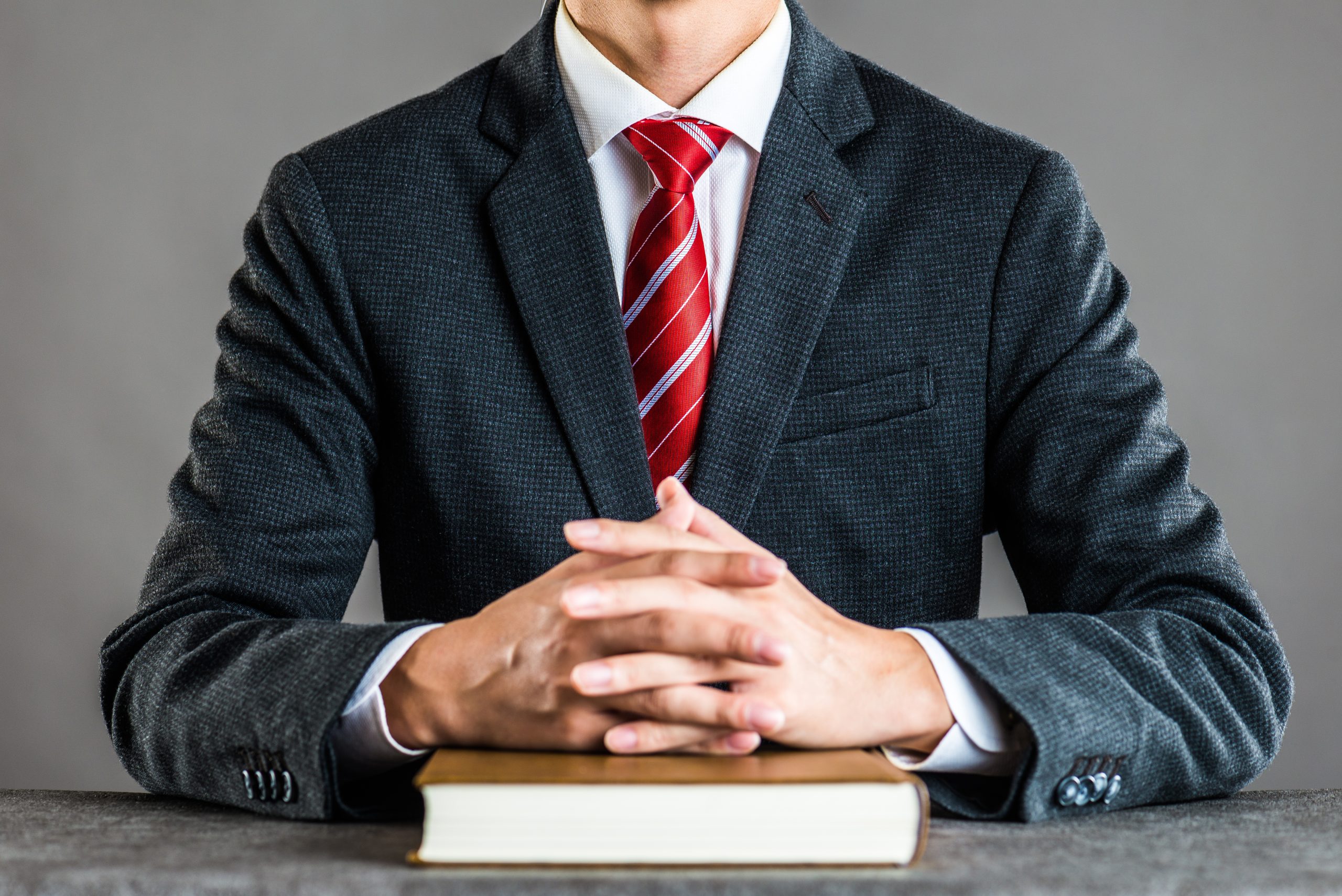
相続登記の義務化は、日本における所有者不明土地問題を解消するために導入されました。
所有者不明土地とは、登記簿上の所有者が不明である土地のことを指します。
この問題は、不動産の相続が行われても登記がなされないことにより、実際の所有者が特定できなくなることが主な原因です。
所有者不明土地の増加は、都市開発や公共事業の進行を妨げるだけでなく、地域の治安や環境問題も引き起こします。
義務化後の変化
2024年4月1日から相続登記が義務化されることにより、相続による不動産の名義変更が必須となります。
この新たな法制度にはいくつかの重要なポイントがあります。
義務化の対象
- 法改正後に発生した相続だけでなく、過去の相続も対象となります。
- すべての相続人が、相続発生から3年以内に登記を行う必要があります。
期限と罰則
- 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
- 正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科せられます。
相続人申告登記
相続人申告登記制度が新設され、相続登記をすぐに行えない場合に利用できます。
相続が発生したことと自分が相続人であることを法務局に申告することで、登記義務を履行したとみなされます。
これにより、相続登記の期限内に手続きを完了できない場合でも、罰則の適用を回避できます。
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消に向けた重要な手順です。
新しい法制度により、相続人は適切な期限内に相続登記を行う義務を負い、罰則が適用されるリスクも増大します。
相続登記が未了の場合は、早めに手続きを進め、必要に応じて相続人申告登記を利用することでリスクを回避しましょう。
疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続した不動産の名義変更手続きである「相続登記」が義務化されました。 これまで放置されていた相続登記ですが、今後は所有者不明土地の増加抑制や、相続トラブルの防止などの効果が期待されています。 そこで今回は、相続登記義務化のポイントを[…]
過去の不動産も対象

2024年4月1日から施行される相続登記の義務化は、将来の相続だけでなく、過去に発生した相続も対象となります。
これにより、既に相続が発生している不動産についても、適切に登記を行う必要があります。
この新制度の詳細とその影響について見ていきましょう。
過去の相続も相続登記義務の対象
新しい相続登記義務化法は、施行日である2024年4月1日以降だけでなく、それ以前に発生した相続についても遡って適用されます。
過去に不動産を相続したが登記を行っていない場合も、義務化の対象となるため注意が必要です。
適用範囲
令和6年4月1日以前に発生した相続も全て対象です。
過去に相続した不動産についても、法施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
登記の期限
相続登記義務化に伴い、相続登記には明確な期限が設定されました。
具体的な期限は次の通りです。
- 基本期限: 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
- 過去の相続: 改正法の施行日(2024年4月1日)から3年以内
これにより、過去の相続に関しても2027年3月31日までに相続登記を完了しなければなりません。
罰則
相続登記を期限内に行わない場合、罰則が適用されます。
正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科されます。
すぐに相続登記ができない場合の対策
相続登記を直ちに行えない場合には、「相続人申告登記」という救済措置があります。
これは、相続が発生したことと自分が相続人であることを申告する制度です。
相続人申告登記のメリット
- 相続登記義務の履行を証明できる
- 罰則を回避できる
ただし、相続人申告登記は正式な相続登記の代わりにはならないため、遺産分割協議が成立した際には改めて正式な相続登記を行う必要があります。
相続登記義務化により、過去の相続も対象となるため、未登記の不動産を所有している相続人は早急に対応することが求められます。
期限内に登記を完了しないと過料が科されるリスクがあるため、必要に応じて専門家の助けを借りながら適切に対応しましょう。
相続登記に関する疑問や不安がある場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
相続登記の手続き

相続登記は、不動産の相続に伴う名義変更の手続きであり、2024年4月1日から義務化されています。
この手続きを正確に行うことは、後々のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。
ここでは、相続登記の手続きと必要書類について詳しく解説します。
必要書類
相続登記を行う際には、以下の書類を準備する必要があります。
これらの書類を適切に揃えることで、スムーズな手続きが可能となります。
- 戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで): 被相続人が死亡したことを証明するために必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本: 相続人の確定と続柄を証明するために必要です。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票: 被相続人の最後の住所を証明するための書類です。
- 相続人全員の住民票: 登記名義人の住所を証明するために必要です。
- 遺産分割協議書: 相続人全員が署名捺印した書類で、遺産分割の内容を詳細に記載します。印鑑証明書も併せて必要です。
- 遺言書(ある場合): 公正証書遺言であればそのまま利用できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
- 不動産の登記簿謄本: 相続対象となる不動産の登記事項証明書です。
- 固定資産評価証明書: 相続登記の際の登録免許税を算出するために必要です。
手続きの流れ
- 不動産の確認: 相続対象となる不動産を確認し、必要書類を収集します。
- 遺産分割協議: 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。
- 書類の準備: 上記の必要書類を全て揃えます。
- 登記申請書の作成: 法務局の指定様式に従い、相続登記申請書を作成します。
- 法務局への申請: 管轄の法務局へ申請書と必要書類を提出します。
郵送でも受け付けてもらえます。 - 登録免許税の支払い: 固定資産評価額の0.4%の税金を収入印紙で納付します。
- 登記完了の確認: 法務局での審査後、登記が完了したことを確認します。
登記識別情報通知書が発行されます。
相続登記の手続きは、相続人が自ら行うことも可能ですが、手続きが煩雑であるため専門家に依頼することが推奨されます。
特に複雑な権利関係がある場合や、手続きに時間を割けない場合は、司法書士などの専門家に依頼すると安心です。
義務化された相続登記をスムーズに進めるためには、早めの準備と正確な手続きが求められます。
2024年4月1日から施行される相続登記の義務化と簡素化についての新しい法制度は、多くの人々にとって重要な変化をもたらします。 この新制度は、相続による土地や建物の登記手続きを義務化し、より簡便な方法で行うことを可能にすることを目的として[…]
相続登記義務化の変更点

相続登記の義務化に伴い、2024年4月1日から新たな変更点が施行されます。
この改正は、不動産の相続手続きにおいて重要な影響を及ぼすため、正確に理解しておくことが必要です。
以下に、相続登記義務化の主な変更点について解説します。
相続登記の義務化
- 義務化の開始日: 2024年4月1日から施行されます。
相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。 - 適用範囲の拡大: 施行日以前に発生した相続も対象となり、過去に相続した不動産についても義務化の対象となります。
登記申請の期限
相続の開始を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
遺贈による所有権取得も同様に3年以内の申請が必要です。
期限内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科されます。
ただし、正当な理由がある場合は過料の対象外となります。
正当な理由による免除
相続人が多数で書類収集に時間がかかる、遺言の有効性が争われている、相続人が重病である、経済的に困窮している場合などが正当な理由とみなされます。
相続人申告登記制度の導入
相続登記の義務を果たせない場合に、相続人が申告することで義務を果たしたとみなされる制度です。
登記名義人に相続が発生したことと、自分が相続人であることを申告するだけで、罰則を回避できます。
ただし、正式な相続登記ではないため、後に正式な登記が必要です。
住所変更登記の義務化
所有者の住所や氏名の変更も義務化されます。
変更があった日から2年以内に登記を行わなければ、5万円以下の過料が科されます。
住所変更登記は、施行日以前の変更にも適用されます。
施行日から2年以内に変更登記を行う必要があります。
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消を目指す重要な施策です。
新しい法制度により、相続登記の手続きが明確化され、期限内に対応する義務が強化されました。
これにより、相続人は早急に手続きを進め、正当な理由がある場合でも申告制度を利用することで、罰則を回避することが求められます。
相続登記に関する詳細や疑問は、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
相続登記をしないリスク

相続登記が義務化されることで、相続人にとって登記を行わない場合のリスクは増大します。
相続登記を怠ることで生じる主なリスクについて解説します。
権利関係が複雑化し、相続登記が困難になる
相続登記を長期間行わずに放置した場合、次のような問題が発生します。
相続人の増加
時間が経つにつれて、相続人の数が増加し、権利関係が複雑になります。
例えば、初代相続人が亡くなり、その子供たちがさらに相続することで、相続人がネズミ算式に増えることがあります。
協議の難航
相続人全員の合意が必要なため、全員と連絡を取るのが難しくなり、遺産分割協議が困難になります。
特に、相続人の中に行方不明者がいたり、意見が対立したりすると、さらに困難です。
不動産の売却や担保提供ができない
登記簿上の所有者が亡くなったままでは、不動産の売却や担保設定ができません。
売却の制約
相続登記を行わないと、不動産の名義が被相続人のままのため、売却を希望しても実際の所有者と登記上の所有者が一致しないため、売却手続きが進みません。
担保設定の制約
不動産を担保に入れて融資を受ける際も、登記簿上の名義が正確でないと融資を受けることができません。
不動産の差押えリスク
相続人の中に債務を抱えている人がいる場合、差押えのリスクが高まります。
債権者による差押え
法定相続による相続登記は、相続人の債権者が相続人に代わって行うことができ、その結果、その持分を差し押さえることが可能です。
これにより、相続人ではない第三者が権利関係に介入してくる可能性があります。
経済的損失
相続登記をしないことで、経済的な損失を被るリスクがあります。
タイミングを逸する
登記をしないことで、不動産の売却タイミングを逃し、価格が下落する可能性があります。
また、売却がスムーズに進まないことで、予定していた資金計画が狂うリスクもあります。
資産の有効活用ができない
登記が完了していない不動産は、担保に入れることもできず、資産として有効に活用することができません。
相続登記を行わないことは、相続人にとって多くのリスクを伴います。
特に権利関係が複雑化し、不動産の売却や担保提供ができないこと、差押えのリスク、経済的損失など、重大な影響を及ぼします。
相続登記は義務化されることで、これらのリスクを回避するためにも、早めに手続きを行うことが重要です。
相続登記に関して不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続登記をしない方が多い訳

相続登記の義務化が施行されたにもかかわらず、多くの人が相続登記を行わない背景には、いくつかの主要な理由があります。
これらの理由を理解することで、相続登記の重要性を再認識し、適切な対策を講じることが可能となります。
手続きが煩雑
相続登記の手続きは非常に煩雑で、多くの人がその複雑さに直面して手続きを先延ばしにしてしまいます。
必要書類の多さ
戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書など、多くの書類を揃える必要があります。
これらの書類を収集するために役所を何度も訪れる必要があるため、手間がかかります。
法務局への申請
申請書の記載方法も厳格に定められており、書類に不備があると再提出を求められることもあります。
このため、手続きに対する心理的なハードルが高くなります。
費用がかかる
相続登記には費用がかかるため、経済的な理由から手続きを躊躇するケースが多いです。
登録免許税
不動産の評価額に基づいて計算される登録免許税は、相続登記を行う際に国に納める必要があります。
固定資産税評価額の0.4%が一般的です。
専門家の報酬
司法書士や弁護士に手続きを依頼する場合、その報酬も発生します。
報酬は不動産の評価額や相続人の数などによって異なり、場合によっては高額になることもあります。
相続人全員が関与する必要がある
相続登記を行うためには、相続人全員の協力が必要です。
これが手続きを難しくする一因となっています。
相続人間の調整
相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合、全員の署名や捺印を集めるのが難しいことがあります。
特に相続人間で意見の対立がある場合、協議が難航することが多いです。
音信不通の相続人
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、その人の分も含めて手続きを進めるのが困難になります。
相続登記をしない理由として、手続きの煩雑さ、費用の問題、相続人全員の関与が求められる点が挙げられます。
しかし、相続登記を怠ることで生じるリスクも大きいため、早めに対応することが重要です。
手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することで、スムーズに進めることができます。
相続人申告登記

相続登記の義務化に伴い、2024年4月1日から新たに導入された「相続人申告登記」制度は、相続人が登記義務を果たしやすくするための救済策です。
以下では、相続人申告登記の概要、利用するメリット、注意点について詳しく説明します。
制度の概要
相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなり、その相続が発生したことを相続人が法務局に申告する制度です。
これにより、相続人が正式な登記を行う前に、相続が開始された事実を登記簿に記載してもらうことができます。
申告内容
- 「所有権の登記名義人に相続が発生したこと」
- 「自身がその相続人であること」
申告方法
必要書類(戸籍謄本など)を準備し、法務局に申告します。
利用するメリット
相続人申告登記にはいくつかのメリットがあります。
義務履行の証明
申告することで、相続登記の義務を果たしたとみなされます。
これにより、期限内に登記を完了できない場合でも罰則を免れることができます。
単独申請が可能
相続人申告登記は、相続人の一人が単独で申請できます。
これにより、相続人全員の同意が必要な遺産分割協議が整わない場合でも、手続きを進めることができます。
簡素な手続き
必要書類が少なく、相続人であることを証明する戸籍謄本などの基本的な書類のみで申請できます。
注意点
相続人申告登記には注意点もあります。
この制度はあくまで相続が発生したことを記録するものであり、正式な所有権移転登記ではありません。
最終的には、正式な相続登記を行う必要があります。
相続人申告登記を行っただけでは、不動産の売却や担保提供などの権利行使はできません。
正式な相続登記が完了していない限り、第三者に対して所有権を主張することはできません。
相続人申告登記は、相続登記義務を果たすための有効な手段であり、相続人が手続きを進める上での大きな助けとなります。
しかし、最終的には正式な相続登記を行う必要があるため、申告登記後も適切な手続きを進めることが重要です。
相続登記に関して不明点や不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続登記義務違反の手続き

2024年4月1日から施行される相続登記義務化により、相続登記を行わなかった場合には罰則が科されることになります。
相続登記義務を果たさないことで以下のようなリスクがあります。
過料の対象
相続登記を期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科されます。
過料は刑事罰ではなく、行政上の罰金です。
住所変更登記も義務化されており、2年以内に登記を行わなければ5万円以下の過料が科されます。
義務違反が発覚した場合の手続き
登記官による違反事実の把握
法務局の登記官が、相続登記の申請義務違反を発見した場合、過料手続きが開始されます。違反は、遺言書や遺産分割協議書の内容などから明らかになります。
違反者への催告
登記官は違反者に対し、相続登記を行うよう書面で催告します。
催告書は書留郵便で送付され、一定の期限内に登記を行うよう求められます。
過料の通知
違反者が期限内に登記を行わなかった場合、登記官は事件を管轄する地方裁判所に通知し、過料手続きが進められます。
裁判所の判断
裁判所は、登記官からの通知に基づいて、10万円以下の過料を科すかどうかを判断します。
正当な理由がない限り、過料の支払いが命じられます。
正当な理由と例外
過料が科されるのを回避するためには、相続登記を行わない正当な理由が必要です。
正当な理由として考慮されるケースは以下の通りです。
- 相続人が多数で資料収集に時間がかかる場合
- 遺言の有効性や遺産範囲が争われている場合
- 相続人が重病である場合
- 相続人がDV被害者などで生命・心身に危害が及ぶ恐れがある場合
- 経済的困窮により登記申請費用を負担できない場合
手続きの重要性
相続登記を行わないリスクを回避するためには、早期に手続きを行うことが重要です。
以下の対策を講じることが推奨されます。
必要書類の準備
戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書などの書類を早めに揃えることが重要です。
専門家への相談
手続きが複雑である場合、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
相続登記義務違反の手続きについては、過料が科されるリスクがあるため、義務を怠らないことが重要です。
正当な理由がある場合でも、法務局や裁判所の判断を仰ぐ必要があるため、早めに対応し、専門家の助けを借りることが推奨されます。
相続登記を適切に行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。 これにより、不動産を相続した場合には、一定期間内に相続登記を行わなければならなくなります。 この新たな制度は、所有者不明土地の増加を防ぎ、円滑な不動産取引を促進するため[…]
相続登記の義務化についてよくある質問

相続登記の義務化に関するよくある質問について、以下にまとめました。
これらの情報は相続登記の手続きをスムーズに進めるために役立ちます。
相続登記の申請期限はいつから始まりますか?
相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されます。
相続登記の申請期限は、「自身が相続の開始および不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」となります。
この期限内に申請しなければなりません。
もし相続登記を行わなかった場合、どのような罰則がありますか?
正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
過料は行政上の罰則であり、支払わなければならない金銭的な罰金です。
過去の相続分も相続登記の義務化の対象ですか?
はい、過去の相続分も義務化の対象となります。
2024年4月1日以前に発生した相続についても、施行日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
過去に相続した不動産についても、2027年3月末までに登記申請を行う必要があります。
相続登記の申請に必要な書類は何ですか?
相続登記の申請には以下の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印が必要)
- 遺言書(ある場合)
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
相続人申告登記とは何ですか?
相続人申告登記は、相続登記の義務を果たせない場合に相続人が法務局に申告することで、義務を履行したとみなされる制度です。
これにより、期限内に正式な相続登記を行えない場合でも、罰則を回避することができます。
ただし、正式な相続登記の代わりにはならないため、最終的には正式な登記を行う必要があります。
相続放棄をしても相続登記をする必要はありますか?
相続放棄が正式に承認されると、その人は相続人の地位を失い、相続登記の義務も免除されます。
ただし、次順位の相続人に登記義務が生じるため、その相続人が手続きを行う必要があります。
相続登記の義務化に伴い、適切な手続きを行うことが求められます。
不明点や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
早めの準備と適切な対応が、相続登記をスムーズに進めるための鍵となります。
相続登記の義務化についてのまとめ

ここまで相続登記の義務化についてお伝えしてきました。
相続登記の義務化の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する手続きのこと
- 相続登記義務化は、日本における所有者不明土地問題を解消するために2024年4月1日から義務化された
- 相続登記義務違反は2024年4月1日から施行された相続登記義務化により、相続登記を行わなかった場合には罰則が科される
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




