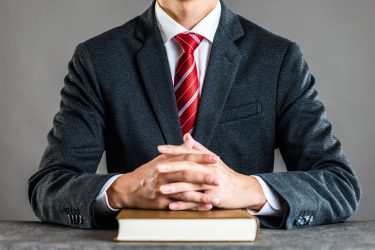2024年4月1日から施行された新法により、相続登記が義務化されました。
これにより、相続が発生した場合、相続人は不動産の相続登記を行うことが法的に求められるようになりました。
しかし、この相続登記の手続きは専門的な知識を必要とし、またそれに伴う費用も発生します。
本記事では、義務化された相続登記の費用について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続登記の義務化とは
- 相続登記にかかる費用
- 相続登記を自分でする場合のデメリット
義務化された相続登記の費用について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地や建物)の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を相続人の名義に変更する手続きのことを指します。
この手続きは、法務局が管理する登記簿(登記記録)に記録されている所有者情報を更新するもので、所有者が亡くなったときには法務局が自動的に名義変更を行うわけではありません。
したがって、所有者が亡くなると、その不動産を相続した方は「相続を原因とする所有権移転登記」、いわゆる相続登記を申請する必要があります。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記を行わないと、相続によって取得した建物や土地などの権利が守られません。
これは、相続登記が行われないと、法的には亡くなった方がまだ所有者であるとみなされるためです。
その結果、相続人が不動産を売却したり、抵当権を設定したりする際に問題が生じる可能性があります。
また、相続登記をしないまま時間が経つと、所有者不明の土地が増えるという社会問題も引き起こします。
したがって、相続登記は費用がかかるし面倒だから、と放置せず、できるだけ早い段階で相続登記の申請手続きを行うことが推奨されています。
相続登記の義務化

日本では、2024年4月1日から、相続による不動産の所有権移転について、相続登記が義務化されました。
これは、所有者不明の土地問題を解消するための重要な措置であり、相続人は「所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
なぜ義務化されたのか
相続登記の義務化は、所有者不明の土地問題を解決するための重要な措置です。
所有者不明の土地は、公共工事の進行を阻害したり、不法占有者が住み着いたりするなど、社会問題となっています。
これらの問題を解消するために、相続登記が義務化されました。
相続登記の義務化により、相続人は「所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
これにより、所有者不明の土地の問題が解消され、不動産の所有権が明確になります。
また、相続登記の義務化は、過去の相続にも適用されます。
これにより、これまでに発生している、相続による不動産の所有権移転についても、相続登記を申請する義務が発生しました。
相続登記にかかる費用

相続登記は、相続人が法的に不動産を所有するための重要な手続きです。
この手続きには、いくつかの費用が発生します。
それらは大きく分けて、「必要経費」と「司法書士の報酬」の2つに分類されます。
不動産の調査費用
不動産の調査は、相続登記の最初の手順であり、相続人が正確に何を相続したのかを把握するために必要です。
この調査には、不動産の位置、面積、構造、評価額など、不動産の詳細な情報を集める作業が含まれます。
これらの情報は、登記簿や固定資産税評価書などの公的な文書から取得します。
この調査費用は、不動産の数や位置により異なります。
各種必要書類の取得費用
相続登記には、多くの書類が必要となります。
これらには、死亡診断書、戸籍謄本、遺言書、相続放棄書などが含まれます。
これらの書類を取得するための費用も、相続登記にかかる費用の一部となります。
登録免許税(法務局への申請費用)
相続登記を完了するためには、法務局への申請が必要です。
この申請には、登録免許税が必要となります。
この税金は、不動産の価値に基づいて計算され、相続登記を行うための公的な手数料となります。
司法書士への報酬
相続登記は、専門的な知識と経験を必要とする複雑な手続きです。
そのため、多くの場合、専門家である司法書士に依頼することが一般的です。
司法書士は、相続登記の全ての手続きを代行し、必要な書類の作成や申請、不動産の調査などを行います。
そのため、司法書士への報酬も、相続登記にかかる費用の一部となります。
以上が、相続登記にかかる主な費用の概要です。
具体的な費用は、相続の状況や不動産の詳細により異なるため、具体的な費用を知るためには、司法書士や専門家に相談することをおすすめします。
相続は一生に一度しか経験しないことが多いため、専門家の助けを借りて、適切な手続きを行うことが重要です。
相続登記は、故人の不動産を相続人に法的に移転させる重要な手続きです。 相続登記の手続きは複雑で、多くの場合、専門的な知識を持つ司法書士の支援が必要となります。 司法書士に相続登記を依頼することは、手続きの正確性を保証し、時間と労力を[…]
相続登記の費用相場に関する具体的な例

相続登記の費用は、地域や条件によって大きく変動します。
以下に、一般的なケースでの相続登記の費用相場について具体的な例を挙げてみましょう。
一般的なケースでの相続登記費用
一般的なケースとは、相続人が複数いて、相続財産に不動産が含まれている場合を指します。
この場合、相続登記の費用は以下のようになります。
- 登録免許税:不動産の価値に応じて決まります。
例えば、不動産の価値が3000万円の場合、登録免許税は約6万円になります。 - 固定資産評価証明書の交付手数料:一般的には、1件あたり400円です。
- 戸籍謄本の交付手数料:一般的には、1件あたり450円です。
- 司法書士の報酬:一般的には、10万円から30万円程度です。
ただし、相続の状況や不動産の数、相続人の数などにより変動します。
これらの費用を合計すると、一般的なケースでの相続登記の費用は、約10万円から40万円程度になるといえます。
地域や条件による費用の変動
地域や条件によって、相続登記の費用は大きく変動します。
例えば、都市部では不動産の価値が高いため、登録免許税が高くなる傾向があります。
また、相続人が多い場合や、相続財産が複雑な場合は、司法書士の報酬が高くなることもあります。
以上のように、相続登記の費用は様々な要素によって変動します。
そのため、具体的な費用を知るためには、自身の状況を詳しく司法書士に相談することが重要です。
また、費用を抑えるための方法も存在しますので、それらについても調査・相談することをおすすめします。
相続登記の費用は誰が負担する?

相続登記の費用負担については、法律上特に決まりはありません。
一般的には、不動産を相続する人が負担することが多いです。
しかし、相続人間で話し合い、合意により負担の割合や方法を決めることが可能です。
現物分割する場合
現物分割とは、相続財産をそのままの形で相続人間で分ける方法を指します。
この場合、不動産を相続する人が相続登記の費用を負担することが一般的です。
しかし、相続人間で話し合い、他の相続人も一部または全額を負担することもあります。
代償分割する場合
代償分割とは、一部の相続人が不動産を相続し、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法を指します。
この場合、不動産を相続する人が相続登記の費用を負担することが一般的です。
しかし、代償金の中に相続登記の費用を含めることも可能です。
代償分割は、遺産相続における複雑な問題を解決するための一つの方法です。 特に、不動産など分割が困難な財産が関わる場合、この手法は相続人間の公平な遺産分配を実現するための鍵となります。 しかし、代償分割を適切に行うためには、そのメカニ[…]
換価分割する場合
換価分割とは、相続財産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける方法を指します。
この場合、相続登記の費用は売却代金から差し引かれ、相続人全員が負担する形となります。
共有分割する場合
共有分割とは、相続財産を共有名義で相続し、その後で分割する方法を指します。
この場合、相続登記の費用は相続人全員が共有する割合に応じて負担します。
以上のように、相続登記の費用負担は相続の形態や相続人間の話し合いにより大きく変わります。
そのため、相続が発生した際には、早期に相続人間で話し合いを行い、費用負担の方法を明確にすることが重要です。
相続登記の手続きの流れ

不動産登記事項証明書を取得する
相続登記の手続きは、まず不動産登記事項証明書の取得から始まります。
これは、相続した不動産の所有権移転を法的に証明するための重要な書類です。
地方法務局や法務局出張所で申請し、必要な手数料を支払うことで取得できます。
不動産登記事項証明書には、不動産の所在地、面積、所有者の名前など、不動産に関する詳細な情報が記載されています。
必要書類を集める
次に、相続登記に必要な書類を集めます。
これには、相続人全員の印鑑証明書、死亡診断書、戸籍謄本などが含まれます。
また、相続人が多数いる場合や、相続人が未成年者や成年被後見人である場合などは、その他の書類が必要になることもあります。
登録免許税を計算する
相続登記には登録免許税が必要です。
登録免許税は、不動産の価値や相続人の数などによって計算されます。
税金の計算は複雑なため、専門家に依頼することも一つの方法です。
相続が発生した際、不動産の法的所有権を正式に移転するためには相続登記が必要です。 この手続きは、故人の不動産を相続人の名義に変更することを目的としており、登記を完了させるためには登録免許税の支払いが伴います。 登録免許税は、不動産の[…]
登記申請書を作成する
必要な書類が揃ったら、次に登記申請書を作成します。
登記申請書には、相続した不動産の詳細や相続人の情報、登記の目的などが記載されます。
申請書の作成には専門的な知識が必要なため、司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
管轄の法務局に申請する
登記申請書が完成したら、管轄の法務局に申請します。
申請は郵送でも可能ですが、直接法務局に持ち込むことで手続きの進行を確認することもできます。
登記完了後の書類を受け取る
最後に、登記が完了したら、法務局から登記完了の通知と登記簿謄本を受け取ります。
これにより、法的に不動産の所有権が移転したことが確定します。
登記簿謄本は大切に保管し、将来的に不動産を売却する際などに必要となることがあります。
以上が、相続登記の手続きの流れです。
手続きは複雑で時間もかかりますが、適切に進めることでスムーズに不動産の所有権移転を行うことができます。
専門家の助けを借りることで、手続きを円滑に進めることが可能です。
相続登記の申請方法

相続登記の申請方法は、相続人が法務局に提出する一連の手続きを指します。
これには、必要な書類の準備、申請書の作成、そして申請手続き自体が含まれます。
ここでは、相続登記の申請方法について詳しく説明します。
法務局で申請
相続登記の申請は、まず最寄りの法務局で行うことができます。
法務局では、専門の職員が手続きをサポートしてくれます。
申請には、相続人全員の印鑑証明書や死亡診断書などの必要書類を持参する必要があります。
また、登記申請書の作成や登録免許税の計算など、専門的な知識が必要な部分もありますので、事前に準備をしておくことが重要です。
郵送で申請
法務局に直接行くことが難しい場合や、時間がない場合は、郵送での申請も可能です。
必要書類を揃え、登記申請書を作成したら、それらを法務局に郵送します。
ただし、郵送での申請は、手続きの進行状況を確認するのが難しいというデメリットがあります。
オンラインで申請
最近では、インターネットを利用したオンラインでの申請も可能になっています。
パソコンやスマートフォンから、必要書類をアップロードし、申請を行うことができます。
オンライン申請のメリットは、いつでもどこでも申請が可能であること、また手続きの進行状況をリアルタイムで確認できることです。
以上が、相続登記を申請する方法についての説明です。
相続登記の申請は、一見複雑に見えますが、しっかりとした準備と理解があれば、スムーズに進めることができます。
自分で申請するメリット・デメリット

相続登記を自分で申請するメリット
相続登記を自分で行う最大のメリットは、費用の節約です。
司法書士に依頼すると、その手数料が発生しますが、自分で行うことでその費用を抑えることができます。
また、自分で申請を行うことで、手続きの流れや必要な書類など、相続登記について深く理解することができます。
これは、将来的に同様の手続きを行う際に役立つ知識となります。
相続登記を自分で申請するデメリット
一方、自分で相続登記を申請するデメリットもあります。
まず、手続きが複雑であり、専門的な知識が必要なため、間違いを犯す可能性があります。
また、必要な書類の準備や申請書の作成など、手続きには時間と労力がかかります。
さらに、自分で申請を行う場合、何か問題が発生したときに自己責任となる点もデメリットといえます。
以上が、相続登記を自分で申請するメリットとデメリットについての説明です。
相続登記の申請は、一見複雑に見えますが、しっかりとした準備と理解があれば、自分で行うことも可能です。
しかし、間違いを防ぐためにも、専門家の助けを借りることを検討することも重要です。
相続登記を司法書士に依頼した方が良いケース

ここでは、司法書士に相続登記を依頼することが適切なケースについて詳しく説明します。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合、相続登記の手続きは複雑になります。
各相続人の意見を調整し、適切な手続きを進めるためには専門的な知識が必要です。
司法書士に依頼することで、スムーズな手続きが可能となり、相続人間のトラブルを避けることができます。
相続する不動産が遠方にある場合
相続する不動産が遠方にある場合、その地域の役所や法務局への訪問が必要となります。
遠方の不動産の相続登記を自身で行うと、移動時間や費用がかさむ可能性があります。
司法書士に依頼することで、これらの手間を省くことができます。
不動産の数が多い場合
不動産の数が多い場合、それぞれの不動産に対する相続登記の手続きが必要となります。
一つ一つの手続きが複雑であるため、全てを自身で行うのは大変です。
このような場合、司法書士に依頼することで、手続きを一元化し、効率的に進めることが可能です。
不動産の権利関係が複雑な場合
不動産の権利関係が複雑な場合、専門的な知識が必要となります。
例えば、共有名義や抵当権が設定されている場合など、自身で解決するのは難しいです。
司法書士に依頼することで、適切な手続きを行い、問題を解決することができます。
遺産分割協議書も同時に作成したい場合
遺産分割協議書を同時に作成したい場合、その作成には法律的な知識が必要です。
司法書士に依頼することで、適切な遺産分割協議書を作成し、相続登記と同時に進めることが可能です。
急いで相続登記をしなければならない場合
急いで相続登記をしなければならない場合、自身で手続きを進めると時間がかかる可能性があります。
司法書士に依頼することで、迅速に手続きを進めることができます。
また、手続きのミスを防ぐことも可能です。
以上のようなケースでは、相続登記を司法書士に依頼することが有効です。
専門的な知識と経験を持つ司法書士に依頼することで、スムーズかつ適切な手続きが可能となります。
相続登記は重要な手続きであるため、適切な対応が求められます。
そのため、自身で行うのが難しい場合は、専門家に依頼することをおすすめします。
義務化された相続登記の費用についてよくある質問

義務化された相続登記の費用に関する疑問は多岐にわたり、適切な情報を得ることが重要です。
以下は、義務化された相続登記の費用についてよくある質問と、その回答をまとめたものです。
Q1: 相続登記にかかる費用はどのくらいですか?
相続登記にかかる費用は主に3つあります。
まず、必要な証明書の取得費用があります。
これには戸籍謄本や固定資産評価証明書などが含まれ、それぞれ数百円から数千円がかかります。
次に、登録免許税があります。
これは不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、一般的には固定資産税評価額の0.4%がかかります。
最後に、司法書士に依頼した場合の報酬があります。
これは一般的に5万円から15万円程度とされています。
Q2: 相続登記の手続きを自分で行うことは可能ですか?
相続登記の手続きは自分で行うことも可能ですが、専門的な知識が必要となります。
また、手続きには時間と労力がかかります。
そのため、相続関係が複雑な場合や、法務局が遠方にある場合などは、専門家に依頼することをおすすめします。
Q3: 司法書士に依頼するメリットは何ですか?
司法書士に依頼するメリットは、手続きのスムーズさと確実性です。
司法書士は相続登記の手続きに精通しており、必要な書類の準備から申請までを一貫して行います。
また、専門的な知識を持つ司法書士に依頼することで、手続きのミスを防ぐことができます。
Q4: 相続登記に必要な書類は何ですか?
相続登記に必要な書類には、戸籍謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などがあります。
これらの書類は、相続人の確定や不動産の評価額の確認、相続人間の遺産分割の合意など、相続登記の手続きに必要不可欠です。
Q5: 相続登記の申請期限は何ですか?
2024年4月1日から施行された新法では、相続登記の申請期限は、「自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内」と定められています。
この期限を過ぎてしまうと、罰則が適用される可能性があります。
Q6: 相続登記の罰則は何ですか?
相続登記の申請を期限内に行わなかった場合の罰則は、「10万円以下の過料」と定められています。
ただし、正当な理由があれば罰則の対象にはなりません。
Q7: 相続登記の申請はどこで行いますか?
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
例えば、沖縄県那覇市に土地を所有していた父親が死亡し、東京都在住の長男が相続した場合、相続登記を申請する法務局は那覇市の法務局となります。
Q8: 相続登記にかかる費用はどのように計算されますか?
相続登記にかかる費用は、必要な証明書の取得費用、登録免許税、司法書士の報酬から計算されます。
証明書の取得費用は各証明書の発行手数料によります。
登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%で計算されます。
司法書士の報酬は一般的に5万円から15万円程度とされています。
Q9: 相続登記の手続きにかかる時間はどのくらいですか?
相続登記の手続きにかかる時間は、相続関係の複雑さや必要な書類の数などによりますが、一般的には数ヶ月程度となります。
ただし、専門家に依頼した場合は、手続きがスムーズに進むため、時間を短縮できる可能性があります。
Q10: 相続登記の手続きを自分で行うデメリットは何ですか?
相続登記の手続きを自分で行うデメリットは、専門的な知識が必要となること、手続きに時間と労力がかかること、手続きのミスが生じる可能性があることなどが挙げられます。
これらの理由から、相続関係が複雑な場合や、法務局が遠方にある場合などは、専門家に依頼することをおすすめします。
義務化された相続登記の費用についてのまとめ

ここまで、義務化された相続登記の費用についてお伝えしてきました。
義務化された相続登記の費用の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続登記の義務化とは、2024年4月1日から、相続による不動産の所有権移転について相続登記が義務化されたこと
- 相続登記にかかる費用は、不動産の調査費用・各種必要書類の取得費用・登録免許税・司法書士への報酬など
- 相続登記を自分でする場合のデメリットは、専門的な知識が必要となること、手続きに時間と労力がかかること、手続きのミスが生じる可能性があることなど
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。