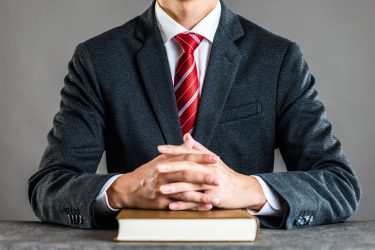たとえ夫婦関係が解消されていても、子どもと親子の関係は血縁上断たれるわけではありません。
そのため、法定相続人として、遺産を相続する権利を持つのです。
しかし、具体的な相続割合や、遺産分割となると、話は少し複雑になってきます。
そこで今回は、離婚した前妻の子どもの相続権について、わかりやすく解説します
- 前妻の子は、相続人になるのか?
- 前妻との子どもとの相続の進め方や注意点
- 前妻の子に相続させたくない場合は
離婚した前妻との子どもの相続権について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
前妻の子は、相続人になるのか?

法律上は親子関係は切れないため、前妻の子にも相続権があります。
これは、たとえ離婚していても、親子の間には血縁関係が存在し、親には子が生まれた時点で扶養義務が発生するためです。
しかし、実際に相続となると、様々な問題が生じてきます。
相続権の基本的な考え方
被相続人が遺言書を残していた場合、その遺言書の内容に基づいて相続財産が分配されます。
遺言書があれば、自分の意思通りに財産を分配することができるため、円滑な相続を実現しやすくなります。
遺言書がない場合、民法で定められた法定相続人の順位に従って相続財産が分配されます。
法定相続人の順位は以下の通りです。
- 配偶者
- 第1順位相続人:子(またはその代襲相続人)
代襲相続人とは、被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子の代わりにその子が相続人となることを指します。
- 第2順位相続人:直系尊属(両親等)
- 第3順位相続人:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
前妻は相続人ではないが、前妻の子は相続人になる
離婚しても、前妻の子と親との親子関係は消滅しないため、法定相続人として遺産を相続する権利があります。
ただし、前妻自身は相続人ではありません。
離婚によって夫婦関係が解消されるため、前妻は配偶者としての相続権を失うからです。
前妻の子に、相続で連絡しないとどうなる?
前妻の子に連絡せずに遺産分割協議を進めると、協議が無効となり、後々トラブルに発展する可能性が高いです。
被相続人と前妻の子が音信不通だったとしても、法定相続人であることに変わりはありません。
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要であり、誰か一人でも欠けると協議は無効となってしまいます。
前妻の子の連絡先がわからない場合でも、戸籍謄本や附票などから調査を進めることで、住所を特定できる可能性があります。
どうしても自分で調査するのが難しい場合は、弁護士などの専門家に依頼することもできます。
法定相続人の範囲と相続分

遺産を誰がどのように受け継ぐのか、多くの方にとって分かりにくいのが現状です。
そこで今回は、法定相続人の範囲と順位について、分かりやすく解説します。
法定相続人の範囲と順位
法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の遺産を相続できる人のことです。
遺言書が存在しない場合、基本的には法定相続人たちが集まり、遺産の分割方法について話し合い、どのように相続を進めるかを決定します。
法定相続人は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 配偶者:被相続人との婚姻関係が存続している者は、常に法定相続人となります。
- 直系卑属:被相続人から血縁的につながる子孫。具体的には、子ども、孫、ひ孫などが該当します。
- 直系尊属:被相続人の父母、祖父母、曾祖父母など、被相続人から血縁的につながる先祖。
法定相続人は、上記の通り3つのグループに分けられますが、さらにそれぞれの中で順位が定められています。
配偶者は常に1順位で、直系卑属は、被相続人から最も近い世代から順に1順位、2順位、3順位と続きます。
例えば、被相続人に子どもが2人いる場合は、子ども2人が1順位となります。
子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもの子ども(孫)が代襲相続人となります。
この場合、孫は2順位となります。
直系尊属は、被相続人に最も近い世代から順に1順位、2順位、3順位と続きます。
例えば、被相続人の両親が存命の場合は、両親が2順位となります。
親がすでに亡くなっていて、祖父母が存命の場合は、祖父母が2順位となります。
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安となる割合です。
相続人が複数いる場合、それぞれの相続人が取得できる遺産の割合を定めています。
法定相続分は、相続人の組み合わせによって以下の通り異なります。
配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者:2分の1
- 子:2分の1(子が複数いる場合は、人数で均等に分割)
配偶者と直系尊属親が相続人の場合
- 配偶者:3分の2
- 直系尊属親:3分の1(親が複数いる場合は、人数で均等に分割)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で均等に分割)
なお、法定相続分はあくまで目安であり、遺言書で自由に定めることができます。
相続が発生すると、遺産をどのように分割するかが重要な問題となります。 日本の民法では、法定相続分という概念が定められており、遺産分割の基本的なルールとなっています。 法定相続分とは、被相続人(亡くなった方)が遺言を残していない場[…]
前妻との子どもとの相続の進め方や注意点
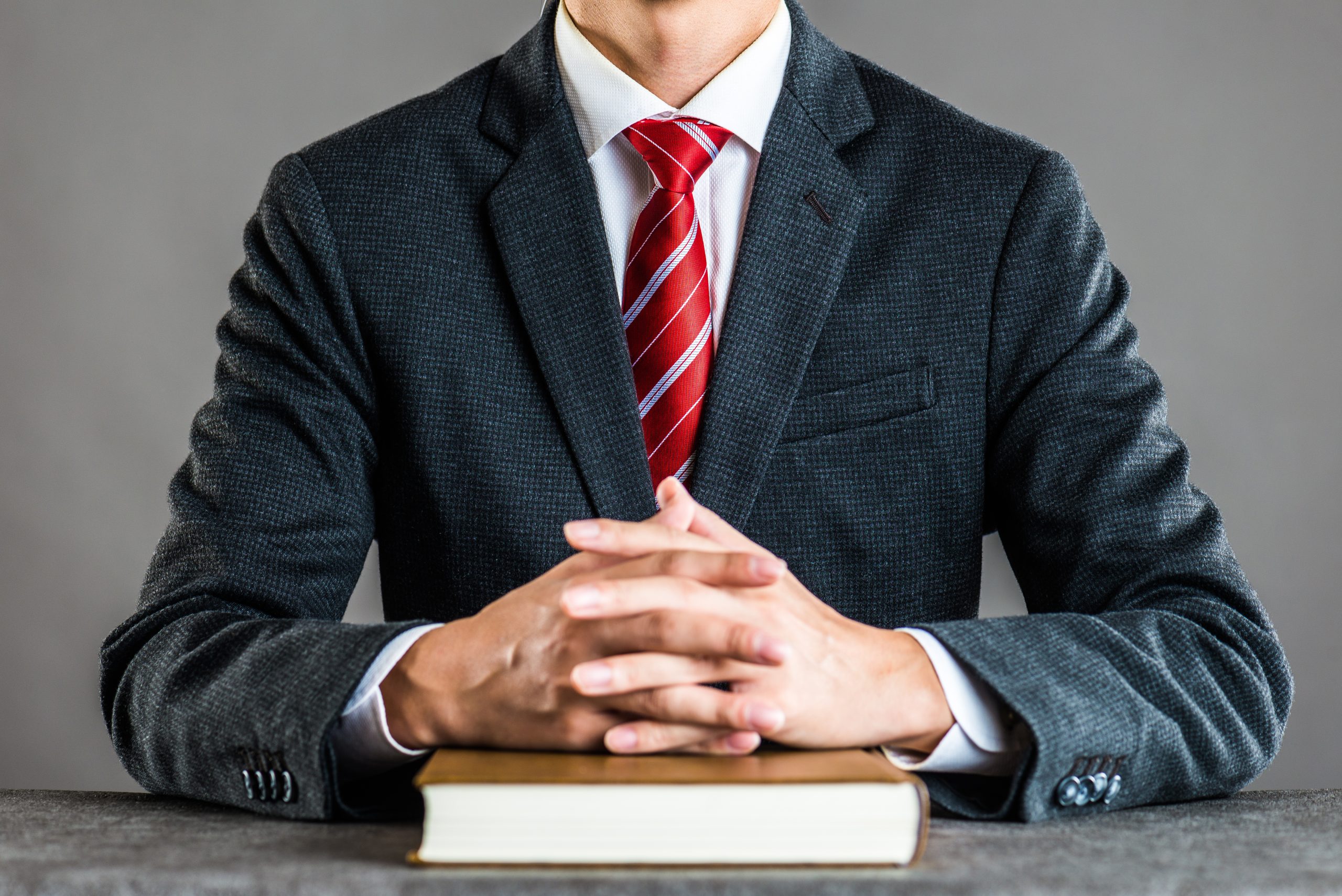
離婚後であっても、前妻との間に生まれた子どもは、父親の遺産相続において重要な役割を果たします。
しかし、離婚という状況が複雑さを加え、相続手続きをスムーズに進めるためには、特有の注意点が存在します。
離婚した前妻との子どもを除外して、相続手続きを行うことはできない
離婚していても、前妻との子どもは法定相続人であり、相続権を持っています。
法定相続人とは、法律で定められた遺産を受け継ぐ権利を持つ人のことです。
遺産分割協議は、相続人全員が合意した上で遺産を分配する手続きです。
もし、離婚した前妻との子どもが遺産分割協議に参加していない場合、その協議は無効となり、遺産分割自体がやり直しになります。
さらに、たとえ遺産分割協議で前妻との子どもが何も相続しないと合意した場合でも、その子どもには「遺留分」と呼ばれる権利が存在します。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け継ぐことができる財産の割合です。
つまり、離婚した前妻との子どもを除外して相続手続きを進めることは、法的に不可能であり、トラブルの元となる可能性が高いです。
離婚した前妻との子どもがいるときの相続手続きの進め方
離婚した前妻との間に子どもがいる場合の相続手続きは、再婚相手やその子どもとの関係性も絡み、複雑になりやすいものです。
円満に進めるためには、以下の点に注意しましょう。
相手に丁寧に接する
離婚しているとはいえ、かつての家族であり、子どもにとっても母親であることに変わりはありません。
感情的にならず、冷静かつ丁寧に接することが重要です。
相続財産の範囲や内容を明確にする
隠し事や虚偽の情報は、不信感を招き、トラブルの元となります。
財産目録を作成し、丁寧に説明しましょう。
遺産分割協議を積極的に進める
法定相続分に基づき、遺産を分割するのが基本です。
離婚した前妻の子どもにも相続権がありますので、その権利を尊重した上で話し合いを進めましょう。
話し合いがまとまらない場合は、調停や審判を利用する
協議が難航する場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することができます。
裁判所の場において、中立的な立場から遺産分割の方法を決定します。
離婚した前妻との子どもが未成年者の場合の遺産分割協議の進め方
未成年の子どもは、自身が遺産分割協議に参加することはできません。
代わりに、親権者または未成年後見人が法定代理人として協議に参加し、遺産分割協議に参加して署名を行います。
前妻の子に相続させたくない場合は

前妻との間に生まれた子がいる場合、その子も法定相続人となり、財産の一部を相続する権利を持っています。
そこで今回は、前妻の子に相続させたくない場合にどのような対策があるのかについてご紹介します。
遺言書をつくる
再婚している場合、遺言書を作成することで、後妻と子供に財産を相続させることができます。
法定相続では、前妻の子にも相続権があるため、遺言書がないと、前妻の子が遺産の一部を相続してしまう可能性があります。
遺言書があれば、遺産分割協議の必要もなくなり、スムーズに相続手続きを進めることができます。
ただし、前妻の子には遺留分という権利があるため、遺言書の内容によって遺留分を侵害していると判断された場合、前妻の子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
遺留分対策としては、前妻の子に遺留分相当額の財産を遺贈する、遺留分放棄の同意を得るなどの方法があります。
生前贈与する
前妻の子に遺産を相続させたくない場合、有効な手段の一つとして生前贈与があります。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与する行為です。
相続とは異なり、贈与税がかかりますが、後妻や後妻の子に財産を渡すための有効な手段です。
死後に相続放棄をしてもらう
被相続人が亡くなった後、相続人となった方が、自己の利益のために相続を辞退する手続きを「相続放棄」といいます。
被相続人に前妻の子がいる場合、その方々に相続放棄をしてもらうことも可能です。
しかし、相続放棄は本人の意思による手続きであり、強制することはできません。
前妻の子が相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
申述書には、被相続人との続柄、相続放棄の理由などを記載する必要があります。
また、被相続人の戸籍謄本や住民票謄本、申述人自身の戸籍謄本などの添付書類も必要となります。
相続人廃除を行う
相続人廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった相続人を、家庭裁判所の審判で相続人としての地位を剥奪する制度です。
制度の概要
- 目的:被相続人に対する不法行為を行った相続人から遺産を相続させないこと
- 手続:生前または遺言で被相続人が家庭裁判所に申し立て
- 審判:家庭裁判所が虐待等があったかどうか、廃除が妥当かどうかを判断
- 効果:廃除が認められれば、当該相続人は相続人としての権利を失う
遺留分が認められる場合がある

前妻の子であっても、後妻の子と同様に遺留分が認められます。
遺留分とは、民法で定められた相続人の最低限度の相続財産を取得する権利です。
具体的には、法定相続分の2分の1を請求することができます。
遺留分とは
遺留分とは、民法で定められた、一定の相続人に対して保証されている最低限の相続財産のことです。
被相続人の死後、遺された相続人の生活を保障するために、一定範囲の相続人に対し、遺留分を求める権利を定めているのです。
被相続人の配偶者や子ども、親、祖父母など一定の相続人に、遺言書の内容にかかわらず、最低限の遺産を取得する権利を保障しています。
たとえ遺言書で「すべてを〇〇に譲る」と書いてあっても、遺留分権利者は遺留分の額を請求することができます。
遺留分侵害請求
遺言書で前妻の子に相続をさせない旨が記載されていたとしても、前妻の子は遺留分を侵害されたとして、遺留分額を請求することができます。
遺留分侵害請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害者に対して遺留分額の支払いを求める請求です。
遺留分額の計算方法
遺留分額は、以下の式で計算することができます。
- 遺留分額=(法定相続分×相続財産)÷2
例
- 相続人が前妻の子1人と後妻の子2人の場合
- 前妻の子の法定相続分:3分の1
- 前妻の子の遺留分:3分の1×2分の1=6分の1
- 遺産が6000万円の場合、前妻の子の遺留分額:6000万円×6分の1=1000万円
遺留分侵害請求の注意点
遺留分侵害請求は、被相続人を知った日から1年以内にしなければなりません。
遺留分侵害請求をするためには、弁護士に相談することをおすすめします。
その他
遺留分に関する詳細は、弁護士や司法書士にご相談ください。
遺言書を作成することで、遺留分侵害請求を回避することができます。
本記事では、相続遺留分について以下の点を中心にご紹介します! 遺留分とは 遺留分を主張する権利を持つ相続人 遺留分侵害額請求の時効 相続遺留分について理解するためにもご参考いただけると幸いです。 ぜひ最後までお[…]
前妻の子との間で起きやすい相続トラブルとは

離婚後であっても、前妻との間に子供がいる場合、相続においては様々なトラブルが発生する可能性があります。
ここでは起こりやすいトラブルについてみていきます。
前妻の子と連絡が取れない
亡くなった方が前妻の子と音信不通だった場合、遺産分割協議を進めるために、後妻や後妻の子が前妻の子と連絡を取ることが重要になります。
しかし、実際には連絡先が分からない、あるいは連絡しても無視されるなど、様々な問題が生じるケースも多くあります。
前妻の子の連絡先が分からない場合は、戸籍の附票を取得することで、現住所を調査することができます。
戸籍の附票は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。
申請には、亡くなった方の戸籍謄本と、手数料が必要です。
前妻の子と連絡が取れないことで、遺産分割協議が難航している場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
前妻の子が相続手続きに協力してくれない
前妻の子が相続手続きに協力してくれない場合、円滑な遺産分割協議や相続手続きを進めるために、以下の方法を検討することができます。
実際に見ていきましょう。
弁護士に相談する
弁護士は、遺産分割協議や相続手続きに関する専門家であり、法的なアドバイスやサポートを受けることができます。
また、前妻の子との交渉や代理人としての対応なども依頼することができます。
相続は、法的な複雑さと個人的な感情が交錯するデリケートな問題です。 このような状況では、適切な法的サポートが不可欠となります。 特に弁護士は、相続問題において中心的な役割を果たし、法的なアドバイス、紛争の解決、遺産分割協議のサポート[…]
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停は、裁判官が間に入って相続人同士の話し合いを促す手続きです。
時間をかけて話し合う
前妻の子が遺産分割協議に協力してくれない理由は、様々考えられます。
感情的なわだかまりがある、遺産の内容に納得していない、相続手続きが面倒くさいと感じている、などが考えられます。
このような場合は、前妻の子と時間をかけて話し合い、互いの意見を理解し合うことが重要です。
話し合いの場としては、弁護士や家庭裁判所の調停委員立ち合いのもとで行うこともできます。
相続手続きは、被相続人にとっても相続人にとっても、大きな負担となるものです。
しかし、円滑に進めるためには、早め早めに準備をしておくことが大切です。
前妻の子に相続権は?
前妻の子にも相続権があります。
たとえ後妻と後妻の子が「前妻の子とは疎遠だったから」などの理由で、前妻の子に遺産を渡したくないと考えても、法的に認められる範囲でのみしか排除することはできません。
相続が発生したことを隠したり、遺産の金額や内容を前妻の子に隠して相続手続きを進めようとしたりすると、不信感を与え、遺産分割調停などに発展する可能性が高くなります。
「住み続けた家を相続したい」など、前妻の子にも相続に関する希望がある場合は、真摯に説明し、納得してもらえるように話し合いましょう。円満な解決を目指すことが重要です。
離婚した前妻との子どもの相続権についてまとめ

ここまで離婚した前妻との子どもの相続権についてお伝えしてきました。
離婚した前妻との子どもの相続権をまとめると以下の通りです。
- たとえ離婚していても、親子の間には血縁関係が存在し、法律上は親子関係は切れないため、前妻の子にも相続権がある
- 離婚した前妻との子どもを除外して、相続手続きを行うことはできないことや相手に丁寧に接するような進め方をする
- 前妻の子に相続させたくない場合は、遺言書をつくることや生前贈与をするなどの方法がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。