生前贈与の非課税枠が2500万円までについて気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、生前贈与の非課税枠が2500万円までについて以下の点を中心にご紹介します!
- 生前贈与とは
- 生前贈与の非課税枠とは
- 相続時精算課税制度とは
生前贈与の非課税枠が2500万円までついて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。

スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
生前贈与とは

生前贈与とは、財産を相続が発生する前に、贈与者が自分の財産を他の人(主に親族)に譲渡することを指します。
相続税対策として活用されることが多いですが、贈与税がかかる場合もあるため、注意が必要です。
また、贈与契約を交わすことで、贈与を受けた側の資産形成にも影響を与えるため、計画的な実施が求められます。
生前贈与は生きている間に財産を贈与することです。 そして、生前贈与の制度は節税に効果があります。 本記事では生前贈与について以下の点を中心にご紹介します。 生前贈与とは 生前贈与のメリット 生前贈与の注意点 […]
生前贈与の非課税枠とは

生前贈与の非課税枠とは、贈与者が生前に財産を贈る際に、一定の金額まで非課税で贈与できる制度のことです。
贈与税は、一定金額を超える贈与に対して課税されるため、非課税枠をうまく活用することで、贈与税の負担を軽減することができます。
例えば、年間110万円までは、贈与税がかからず、贈与者が何度でもこの金額を贈与することが可能です。
これにより、贈与を受ける人が税負担を気にせずに資産を受け取ることができます。
また、特定の条件を満たす場合には、贈与税が非課税となる場合もあります。
大切な方の遺産を円滑に分割するためには、遺産分割協議書の作成が欠かせません。 しかし、初めて作成する場合は、何をどのように書けば良いのか迷ってしまうことも多いでしょう。 また、作成方法や内容に不備があると、トラブルに発展してしまう可[…]
相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、贈与者が生前に財産を贈る場合、その際の贈与税を一定の非課税枠まで免除し、残りの贈与分に対して課税される仕組みです。
ただし、贈与を受けた財産の評価額は、将来の相続の際に合算して再計算され、相続税として精算されます。
この制度では、累計で2,500万円までの贈与が非課税となり、超過分については一律20%の税率が適用されます。
主に生前贈与を活用して相続対策を進めたい人に利用されていますが、制度を適用する際には税務署への届出が必要です。
また、利用後は暦年贈与(年間110万円の非課税枠)が使えなくなるため、長期的な税負担を見据えた計画的な運用が求められます。
相続税計画は、我々の生活において重要な役割を果たします。 その中でも、特に注目すべきは贈与税の課税制度の選択です。 本記事では、相続時精算課税制度について以下の点を中心にご紹介します! 相続時精算課税制度 相続時[…]
相続時精算課税制度の手続き

相続時精算課税制度を利用するには、一定の手続きを経る必要があります。
この制度を選択することで、事前に贈与を行い、将来の相続税を効率的に管理できますが、申請には正確な準備と書類の提出が求められます。
手続きの流れ
贈与契約の締結
贈与者と受贈者の間で贈与内容を明確にする契約を交わします。贈与内容や金額を記載し、双方の合意を確認することが重要です。
税務署への届出
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、相続時精算課税制度の適用申請書を税務署に提出します。この申請をもって制度の利用が開始されます。
贈与税の申告と納付
非課税枠(2,500万円)を超えた贈与額については、20%の税率で贈与税を計算し、申告・納付します。
相続発生時の精算
相続が発生した際に、贈与財産とその他の遺産を合わせ、相続税の計算を行います。すでに支払った贈与税は相続税から控除されます。
必要な書類
相続時精算課税選択届出書
制度の適用を申請するための基本的な書類です。
贈与税の申告書
贈与が行われた年の翌年に提出する必要があります。
贈与契約書の写し
贈与内容を明確にするため、贈与者と受贈者が締結した契約書を添付します。
贈与者および受贈者の戸籍謄本
贈与者と受贈者の続柄を証明するために提出が必要です。
財産の評価額を証明する書類
贈与した財産の価値を確認するため、不動産であれば固定資産評価証明書、金融資産であれば残高証明書などを用意します。
事前に専門家と相談し、正確に書類を準備することが、手続きをスムーズに進めるためのポイントです。
相続時精算課税制度のメリット

一度に2500万円までの贈与が可能になる
相続時精算課税制度では、特定の条件を満たす場合、一度に最大2500万円までの非課税贈与が可能です。
このため、生前贈与を活用して資産を次世代に移しやすくなり、大きな金額の資産移動も柔軟に対応できます。
2500万円を超える贈与の税率が低くなる
2500万円を超える部分についても、一律20%の税率で贈与税が課されます。
この税率は累進課税が適用される通常の贈与税よりも低く設定されており、大きな贈与を行いたい場合にも税負担を抑えることが可能です。
相続税の基礎控除内だと贈与税も相続税もかからない
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、最終的に相続税の計算に含められますが、相続税の基礎控除内であれば、贈与税も相続税も発生しません。
このため、基礎控除の範囲内での贈与が税負担を増やさない選択肢となります。
将来的に相続税の節税につながる可能性が高くなる
相続時精算課税制度を活用することで、資産を早めに贈与することが可能となり、その後の資産の運用益や価値上昇による課税対象額の増加を抑えられる場合があります。
この結果、将来的に相続税の節税につながる可能性が高まります。
相続時精算課税制度のデメリット
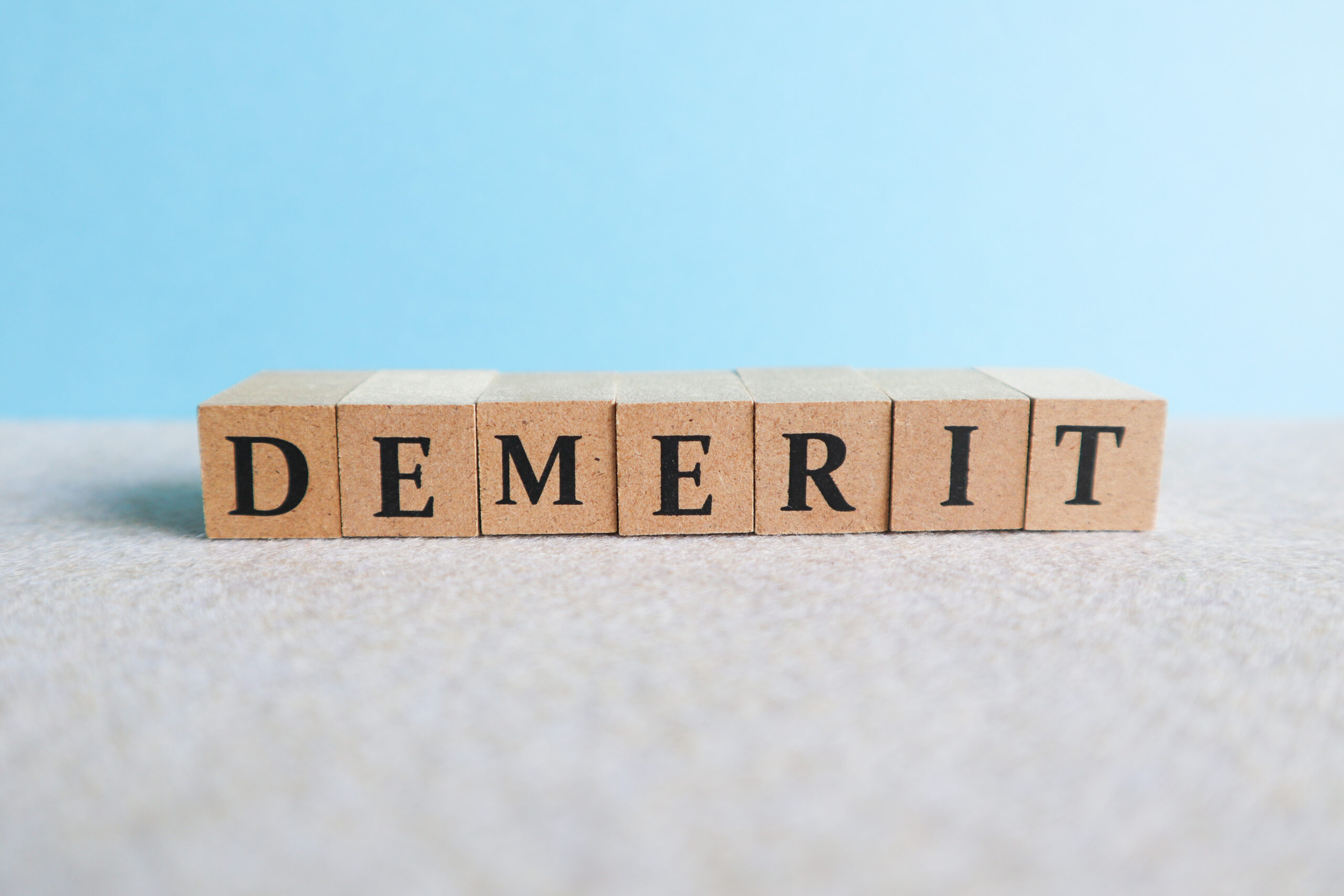
相続時精算課税制度には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。
まず、この制度を利用すると、暦年贈与の非課税枠(年間110万円)を活用することができなくなります。
そのため、長期的に少額ずつ贈与を行うことで税負担を抑える方法を選ぶことが難しくなります。
また、贈与財産の価値が将来下がる場合でも、贈与時の評価額で相続税が計算されるため、不利になる可能性があります。
さらに、この制度を利用すると相続時に贈与財産と他の遺産が合算されるため、相続税の負担が予想より増える場合もあります。
最後に、この制度の利用には税務署への届出が必要であり、一度選択すると取り消しができません。
そのため、事前に十分なシミュレーションと専門家への相談が必要です。
その他の生前贈与の非課税枠
暦年課税の基礎控除
暦年課税では、贈与税の基礎控除として年間110万円までの贈与が非課税となります。
この非課税枠は毎年利用可能であり、計画的な生前贈与を行うことで、税負担を抑えながら資産を少しずつ移転することができます。
教育資金の贈与税の非課税措置
直系尊属(祖父母や父母)から子や孫に対して教育資金を一括贈与する場合、1500万円までの贈与が非課税となる制度があります。
これは、学校の授業料や教材費、その他の教育関連費用に利用することが条件です。
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
結婚や子育てに関連する費用を目的として直系尊属から贈与を受ける場合、1000万円まで非課税となる制度があります。
この制度は、結婚式費用や不妊治療費、出産・育児に関わる費用に適用されます。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
住宅購入や新築、リフォームのための資金として直系尊属から贈与を受けた場合、一定の条件下で最大1000万円(住宅の種類によって異なる)が非課税となります。
この措置は、住宅資金を効率的に受け取る手段として活用されています。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者間で居住用不動産やその購入資金を贈与する場合、2000万円までが非課税となります。
この控除は、一度限りの特例であり、配偶者への生活支援や老後の備えとして利用されています。
特定障害者等に対する贈与税の非課税制度
特定障害者や特定疾病者に対して信託契約を通じて贈与を行う場合、6000万円まで非課税とする制度があります。
この制度は、障害を持つ方の生活を支えるための資金移転を促進することを目的としています。
生前贈与の非課税枠が2500万円までに関してよくある質問

生前贈与で2500万円は税金がかかるの?
生前贈与で2500万円を贈与する場合、贈与税がかかるかどうかは利用する制度によります。
暦年課税では年間110万円を超える部分に対して贈与税が課されますが、相続時精算課税制度を活用すれば、2500万円まで非課税で贈与が可能です。
この制度を利用した際、2500万円を超える部分には一律20%の税率で贈与税が課されますが、相続時にこれらの贈与額を相続財産に合算して相続税を再計算する仕組みです。
制度の利用には事前の申請が必要であり、選択後は暦年課税に戻ることができない点に注意が必要です。
生前贈与は何歳までできる?
生前贈与に年齢制限はなく、贈与者が意思能力を持っている限り、何歳であっても実施可能です。
ただし、高齢になると認知能力の低下などによって贈与の有効性が疑われるケースもあり、トラブルを防ぐために贈与契約書を作成することが推奨されます。
また、特定の非課税措置や制度を利用する場合、受贈者の年齢に条件が設定されていることがあります。
たとえば、教育資金の非課税贈与では30歳未満、結婚・子育て資金の非課税贈与では50歳未満などの制限があります。
そのため、制度利用を検討する際には、受贈者の年齢条件を確認することが重要です。
相続時精算課税制度ってなに?
相続時精算課税制度は、一定の条件を満たす場合に、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に対して行う贈与について、最大で2500万円までを非課税とする制度です。
この制度を利用すると、贈与時点で贈与税の負担を抑えることができ、相続時にこれらの贈与額を相続財産に合算して相続税を計算する仕組みになっています。
贈与税の課税対象となるのは2500万円を超えた分のみで、一律20%の税率が適用されます。
この制度を活用すれば、生前に資産を次世代に移転しやすくなり、相続税の対策を事前に進めることが可能です。
ただし、一度この制度を選択すると暦年課税に戻すことができないため、将来の相続計画を慎重に立てる必要があります。
生前贈与の非課税枠が2500万円までについてのまとめ

ここまで生前贈与の非課税枠が2500万円まであることについてお伝えしてきました。
生前贈与の非課税枠が2500万円までについての要点をまとめると以下の通りです。
- 生前贈与とは、財産を相続が発生する前に、贈与者が自分の財産を他の人(主に親族)に譲渡すること
- 生前贈与の非課税枠とは、贈与者が生前に財産を贈与する際に、一定の金額まで非課税で贈与できる制度のこと
- 相続時精算課税制度とは、贈与者が生前に財産を贈与した場合、その際の贈与税を一定の非課税枠まで免除し、残りの贈与分に対して課税される仕組みのこと
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




